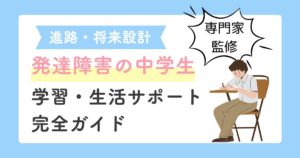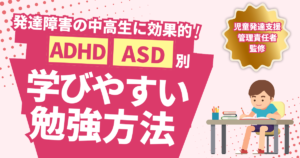「WAIS(ウェクスラー成人知能検査)」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
発達障害や学習面の課題を抱える中高生にとって、この検査は自分の強みと弱みを客観的に把握する大切な手がかりとなります。
しかし、数値の意味や、WISCとの違い、さらに結果を進学や就職にどうつなげればよいのか、専門的な解説を目にする機会は意外と少ないものです。
本記事では、児童発達支援管理責任者として支援現場に関わる立場から、WAISの基礎知識とWISCとの違いを整理しつつ、検査結果を「将来を見通すためのツール」としてどのように活用できるかを解説します。
受験やキャリア選択に不安を抱える保護者や教育関係者に向けて、検査を「可能性を狭めるラベル」ではなく「選択肢を広げる材料」として捉える視点をお伝えしていきます。
WAISとは?発達障害理解に役立つ基礎知識
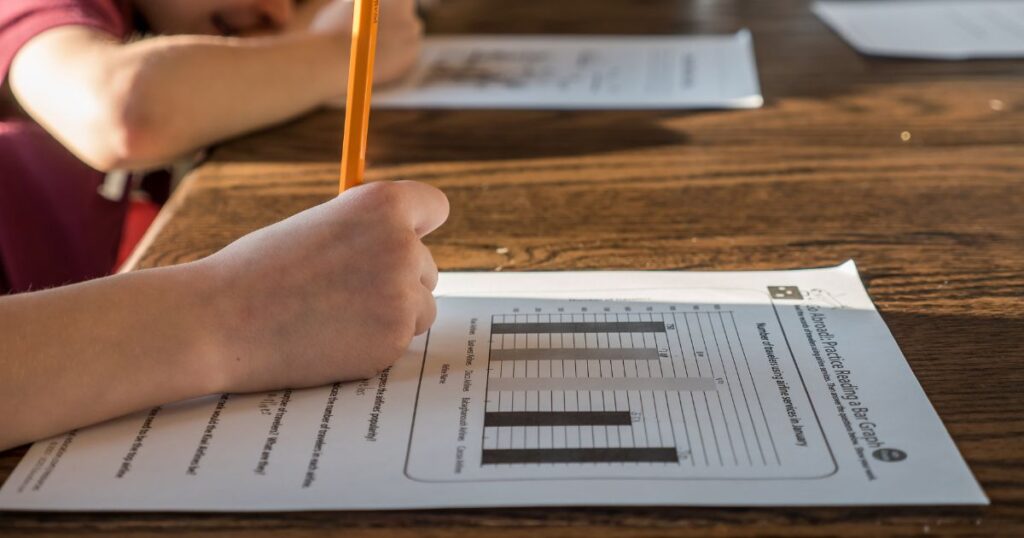
WAIS(ウェクスラー成人知能検査)とは?
WAIS(ウェクスラー成人知能検査)は、16歳以上を対象とした知能検査の国際的な標準です。
単にIQ(知能指数)を算出するためだけでなく、思考や学習の特性を多面的に把握できる点が特徴です。
検査は複数の下位課題で構成され、単語理解や文章把握といった「言語的な能力」から、図形を使った推理やパズルのような「非言語的な能力」まで幅広く評価します。
発達障害がある場合、「成績が伸びないのは能力の問題なのか、それとも学習方法が合っていないのか」という見極めが難しいことがあります。
WAISを実施することで、その子の認知プロファイル(得意と不得意のパターン)を可視化し、学習や生活場面での困難の背景を明らかにすることが可能です。
そのため、教育現場や医療現場だけでなく、進学や就労支援の場でも活用されることが増えています。
測定される4つの領域(言語理解・知覚推理・ワーキングメモリ・処理速度)
WAISは大きく4つの領域を測定します。
- 言語理解(VCI)
-
語彙力、言葉の理解力、知識の応用力を測ります。授業中の説明をどれだけ言語的に理解できるかに直結します。
- 知覚推理(PRI)
-
図形やパターンを手がかりに問題を解決する力です。算数や理科の図形問題、空間認識力などに関連します。
- ワーキングメモリ(WMI)
-
短期間の記憶を保持しながら処理する能力です。黒板の板書を覚えてノートに写す、計算の途中経過を頭に残すといった場面で重要です。
- 処理速度(PSI)
-
視覚情報を正確かつ素早く処理する力です。テストの解答スピードや、日常の作業効率と深く関係します。
発達障害がある子どもでは、この4領域の得点に大きな差が生じるケースが多く見られます。
たとえば、言語理解は高いのに処理速度が極端に遅い場合、理解力は十分でも試験時間に間に合わないといった困難が生じやすくなります。このように「どこでつまずいているか」を数値化できる点が、WAISの大きな強みです。
対象年齢(16歳以上)と中高生への適用範囲
WAISは「成人知能検査」と呼ばれますが、16歳以上の高校生から利用できます。
中学生までは児童用のWISCが標準ですが、高校進学のタイミングでWAISへ移行することで、より現実に近い課題(大人の生活や学習に関連する課題)で認知特性を測定できるようになります。
例えば、高校生で授業についていけない、試験の成績に波がある、進学か就職かで迷っている場合にWAISを受けると、どのような支援や進路選択が適切かを考えるうえで貴重な情報が得られます。
また、大学入試や資格試験で合理的配慮(試験時間延長や問題用紙の拡大など)を申請する際の根拠資料にもなり得ます。
つまりWAISは「大人になる入り口にいる子ども」が、自分の強みと課題を把握し、学習・進路・就職の道筋を立てるために活用できる検査といえます。
WISCとの違い
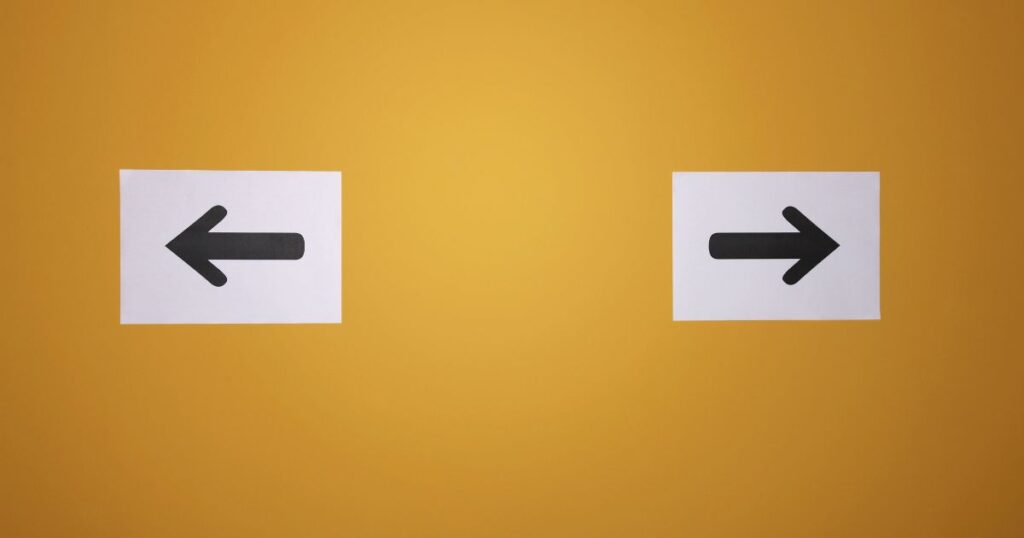
WISC(5~16歳対象)の構成と特徴
WISC(ウィスク:ウェクスラー児童用知能検査)は、5歳から16歳までを対象とした検査で、小中学生の発達特性を把握するために広く用いられています。
構成はWAISと同じく複数の下位検査から成り、言語理解・知覚推理・ワーキングメモリ・処理速度の4領域を測定します。
ただし、WISCは発達途上にある子どもの特性を反映しやすい課題で構成されている点が特徴です。
たとえば、語彙や理解の問題は子どもの生活経験に即した質問が多く、図形課題も子どもが取り組みやすい内容になっています。
そのため「学習にどんなつまずきがあるのか」「年齢相応に発達しているか」を把握するのに適しており、学習支援計画や特別支援教育の指導に直結します。
中学・高校進学期に「WISCからWAISへ」切り替わる意味
中学から高校へ進学する時期は、学習内容が高度化し、また「進学か就職か」といった進路の選択が迫られる重要な時期です。
このタイミングで、従来のWISCからWAISへ切り替えることには大きな意味があります。
WISCは「子どもに合った学習方法を探す」ための検査でしたが、WAISは「大人に近い学習・生活・社会参加のスキルをどう活かすか」を見る検査です。
たとえば、WISCでは年齢に応じた課題で得意不得意を明らかにしますが、WAISではより実社会に近い課題を通して、仕事や資格試験などに直結する認知能力を評価します。
つまり、高校進学期にWAISを受けることは「これからの学習や職業生活に必要な力を客観的に把握する」ためのステップであり、単なる年齢による移行以上の意味を持っています。
発達段階ごとの測定意義と、支援方針への反映
WISCとWAISの違いを理解するうえで大切なのは、単に「対象年齢が違う」という点だけではありません。
両者は「発達段階における課題の見方」が異なります。
- 児童期(WISC):学習基盤の形成期にあり、「読み書き計算のつまずき」「授業への集中困難」「コミュニケーションの未熟さ」など、学校生活の基礎部分を測定・把握します。
- 青年期(WAIS):より複雑な課題に取り組む時期で、「処理速度が遅く試験時間に間に合わない」「ワーキングメモリの弱さで板書が写せない」「問題解決力に差がある」といった、進学や就労の実場面に直結する課題を可視化します。
このように、WISCは「基礎的な学習支援の方向性を決める」ことに役立ち、WAISは「進路や就労を見据えた支援方針を整える」ためのツールとなります。
学校や家庭での支援計画を立てる際、発達段階に応じて適切な検査を選び、得られた結果を現実の教育・生活に結びつけることが重要です。
WAISはどこで受けられる?検査の流れとポイント
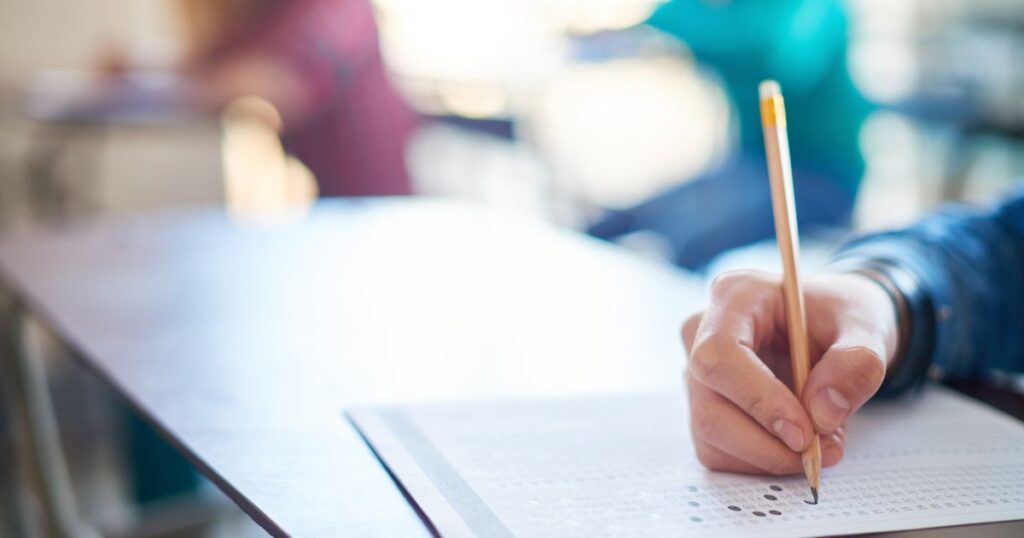
どこで受けられるのか(医療機関・心理相談センターなど)
WAISを受けられる場所は限られており、基本的には専門家が所属する機関に限られます。
もっとも多いのは 精神科や心療内科などの医療機関 で、診断や発達相談の一環として実施されます。
また、自治体の発達支援センターや療育センター、大学附属の心理相談室でも実施している場合があります。
ただし、機関によっては「発達障害の診断が疑われる人のみ対象」「学齢期の子どもはWISCで対応」など条件があるため、事前に問い合わせて確認する必要があります。
学校のスクールカウンセラーや教育センターを経由して紹介されるケースもありますので、まずは身近な相談窓口に聞いてみるのも良い方法です。
検査の流れと所要時間
WAISの検査は、いきなりテストを受けるのではなく、段階を踏んで実施されます。
一般的な流れは以下の通りです。
検査を受ける目的や、現在の困りごと、これまでの発達歴を確認します。
保護者や本人の不安を整理する大切なステップです。
心理士がマンツーマンで下位検査を行います。
課題は言語理解やパズル、数字の記憶、記号探しなど多岐にわたり、所要時間はおよそ90〜120分です。
集中力が続かない場合は、数日に分けて行うこともあります。
検査後は心理士が結果を分析し、得意・不得意のプロファイルをまとめます。
その後、保護者や本人にフィードバック面談を行い、学校や家庭でどのように活かせるかを説明します。
この一連の流れを通じて、単なる数値ではなく「本人にとっての学習や生活上の課題」が明確になります。
結果を次のステップ(進学支援や職場での配慮申請など)にどうつなげるかが大切なポイントです。
費用や保険適用の有無
WAISの費用は、実施する機関によって大きく異なります。
- 医療機関(精神科・心療内科など)で受ける場合
発達障害の診断や治療の一環として行われれば、健康保険が適用されるケースがあります。
その場合、自己負担は3割(自立支援医療制度を利用すれば1割)となり、数千円~1万円程度で受けられることもあります。 - 大学附属の心理相談室や民間の心理相談機関で受ける場合
保険は適用されず、全額自費になります。
費用は機関ごとに異なりますが、一般的に 2万円〜5万円程度 が目安です。
結果のレポート作成や面談を含むかどうかによっても料金が変わります。
受検を検討する際は、「費用の総額」「レポートの有無」「フィードバック内容」を事前に確認しておくことが大切です。
検査は一度受けるだけでも大きな情報を得られるため、安心して受けられる機関を選ぶことが望ましいでしょう。
受ける前に準備しておきたいこと
WAISを受ける前に、日頃の様子やこれまでの経過を整理しておくと、検査がより意味のあるものになります。とくに役立つのは以下の3点です。
- 発達歴の整理:幼少期から現在までの言葉の発達、学習の得意不得意、対人関係の様子などを簡単にまとめておくと、初回面接での説明がスムーズになります。
- 学校での困りごとの記録:授業に集中できない、テストで時間が足りない、宿題の計画が立てられないなど、具体的なエピソードを記録しておくと、検査の解釈に直結します。
- 過去の検査結果や診断の有無:すでにWISCや他の心理検査を受けていれば、その結果を持参することで比較が可能になります。
準備をして臨むことで、単なる数値の把握にとどまらず、「現実の困りごととどうつながっているのか」をより的確に明らかにできます。
検査結果の共有の仕方
WAISの結果を得たあと、誰にどのように伝えるかは非常に重要なポイントです。
- 学校や塾に伝える場合
成績や授業態度に直結する情報であれば、必要な部分だけを抜粋して共有するのが望ましいです。たとえば「処理速度が低いため、テスト時間を延長してもらえると力を発揮できる」といった具体的な支援につながる形で伝えると、先生も理解しやすくなります。 - 職場や支援機関に伝える場合
就職活動や職場定着支援では「結果をそのまま提出する」のではなく、「どんな配慮があると働きやすいのか」という形に整理して伝えることが大切です。例えば「口頭指示では忘れやすいため、書面での指示があると安心」と具体的に説明することで、受け入れてもらいやすくなります。
結果を共有する際には、本人の同意を得ることが前提です。
WAISはラベルを貼るためのものではなく、あくまで「環境を整えて本人の力を最大限に発揮する」ためのツールであることを周囲と共有する姿勢が求められます。
【進学・学習】WAISの結果の活かし方

【学習】得意・不得意の可視化と個別指導への応用
WAISの大きな特徴は「能力を単一のIQで表すのではなく、複数の領域ごとに可視化できる」点です。
発達障害のある中高生は、教科ごとに極端な得意・不得意が見られることが多く、その背景にはワーキングメモリや処理速度などの認知機能の差が関係している場合があります。
例えば、言語理解が高い子どもは国語や社会の暗記学習には強い一方、処理速度が低いと問題量の多い数学や英語の試験で時間切れになることがあります。
逆に、知覚推理が得意な子どもは図形問題や実験課題には力を発揮しますが、語彙力に乏しく説明問題が苦手、というケースもあります。
このような特性が明らかになると、塾や学校での個別指導の内容を本人に合わせて調整できます。
たとえば「板書を取ることに集中させずプリントで補う」「宿題は問題数を減らしても理解度を確認する」など、学習方針を変えるだけで負担が大きく軽減され、学力を伸ばしやすくなります。
【入試・定期試験】ワーキングメモリ・処理速度と試験対策
進学を目指す生徒にとって、試験対策に直結するのがワーキングメモリと処理速度の領域です。
ワーキングメモリが弱いと「問題文を読みながら条件を保持できない」「途中式を忘れてしまう」などの困難が生じます。
一方で処理速度が低いと、理解はできても解答が時間内に終わらず、本来の力を得点に反映できません。
WAISの結果を踏まえると、こうした課題に合わせた具体的な試験対策を講じることができます。
ワーキングメモリが弱い生徒には「問題文に線を引く」「解法の手順をカード化する」といった視覚的補助を導入します。
処理速度が課題の場合は「過去問演習の時間配分を工夫する」「一部の設問を捨てて確実に取れる問題に集中する」といった戦略が有効です。
また大学入試や資格試験では、試験時間の延長や問題用紙の拡大印刷といった合理的配慮を申請できるケースもあります。
その際、WAISの結果が具体的なエビデンスとして役立ちます。
【就活・社会人生活】WAISの結果の活かし方

職場で求められるスキルとWAIS指標の関連性
就職活動を控える発達障害のある若者にとって、WAISの結果は「職場で必要とされるスキル」を具体的に見える化する役割を果たします。
たとえば、処理速度が低い場合は「作業を急かされるとミスが増える」可能性があり、逆に言語理解が高ければ「説明を受けた内容を整理し、周囲に伝える」能力が強みとなります。
職場ではマルチタスク、臨機応変な対応、正確な情報処理などが求められますが、WAISで測定されるワーキングメモリや処理速度はこれらの能力と密接に関係します。
検査結果をもとに「得意なスキルを活かせる業務」「苦手さをカバーできる環境」を選ぶことが、職場定着の第一歩になります。
キャリアカウンセリングや職業適性検討での役割
進学後に就職を見据える段階では、WAISはキャリアカウンセリングの有力なツールになります。
発達障害のある若者は「どんな職種が向いているのか」「どのような環境なら働きやすいのか」を言語化するのが難しいことがあります。
その際、WAISのプロファイルは本人や支援者にとって客観的な手がかりとなります。
例えば、知覚推理が高い場合は図面や設計、空間認識が必要な職種が適している可能性があります。
反対に、処理速度が低いが言語理解が高い場合は、スピードよりも正確さやコミュニケーション力が求められる職種に向いていると判断できます。
このように、検査結果を根拠にキャリアプランを考えることで、本人も「できること」「工夫が必要なこと」を自覚しやすくなり、就労への不安が和らぎます。
障害者雇用枠・合理的配慮を申請する際の根拠資料として
WAISの結果は、障害者雇用枠での就職や合理的配慮を求める際の公式な資料としても役立ちます。
企業が配慮を検討する際には「具体的にどのような困難があるのか」を知る必要がありますが、WAISのプロファイルはその説明に説得力を与えます。
例えば「処理速度が平均より低いため、作業時間の余裕が必要」「ワーキングメモリが弱いため、口頭指示ではなく書面での指示が望ましい」といった要望は、WAISの数値に裏づけされていれば受け入れられやすくなります。
また、公的機関やハローワークの職業カウンセラーに提示することで、職場開拓やジョブコーチ支援にもつながります。
重要なのは、WAISの結果を「制限の証明」としてではなく「適切な環境で能力を発揮するための根拠」として活用することです。
そうすることで、本人の強みを尊重しながら就労の選択肢を広げることができます。
WAISの結果からわかる発達障害の特性

発達障害(ASD・ADHD・LD)における典型的なプロファイル例
WAISの結果は、発達障害の診断と併せて理解することで大きな意味を持ちます。
ASD、ADHD、LDといった発達障害では、しばしば特徴的な得点プロファイルが見られます。
- ASD(自閉スペクトラム症):言語理解は高いが処理速度が低い、または知覚推理が突出して高い一方でワーキングメモリに弱さがある、というように「凹凸の大きなプロファイル」が多く見られます。
- ADHD(注意欠如・多動症):全般的な知能は平均範囲でも、ワーキングメモリや処理速度が低く、集中の持続や作業効率の課題が表れやすいです。
- LD(学習障害):全体IQは十分でも「言語理解」や「処理速度」の一部に顕著な弱さが出ることがあり、読み書きや計算に直結する困難として表面化します。
これらはあくまで典型例であり、個々の結果は多様ですが、「なぜ特定の教科や場面で困難が生じるのか」を説明できる手がかりとなります。
診断そのものとWAISの役割の違い(誤解されやすいポイント)
保護者や教育現場で誤解されやすいのは「WAISを受ければ発達障害かどうか診断できる」という考え方です。
実際には、WAISは診断のための検査の一部に過ぎません。
発達障害の診断は、発達歴、行動観察、心理検査、医師の面接などを総合して行われます。
WAISが果たす役割は「能力のプロファイルを明らかにする」ことであり、それ自体が診断名を与えるものではありません。
むしろ大切なのは、検査で得られた強み・弱みのパターンを、本人の生活や学習支援にどう活かすかです。
診断と混同せず「支援を設計するための地図」としてWAISを位置づける視点が必要です。
WAISの数値を日常や学習にどう活かすか
WAISの結果は数値として示されますが、「高いから安心」「低いから問題」という単純な判断はできません。
重要なのは、数値の“凸凹”が生活や学習にどう影響しているかという点です。
例えば、処理速度が平均より低くても、環境調整によって作業時間を延ばしたり、事前に準備をしておいたりすれば十分対応できます。
逆に、知覚推理が高くてもワーキングメモリが弱ければ「理解できるのに解答に結びつかない」困難が起きることもあります。
つまり、WAISの数値は「能力の優劣を決めるラベル」ではなく「どの場面で工夫が必要かを教えてくれる指標」と捉えるべきです。
支援者や保護者がこの視点を持つことで、本人の自己肯定感を守りながら現実的なサポートにつなげることができます。
検査結果をどう伝えるか?本人・家庭へのフィードバック

本人の自己肯定感を守る伝え方
WAISの結果を本人に伝える際に最も大切なのは、「できない部分の指摘」ではなく「得意をどう活かせるか」に焦点を当てることです。
発達障害がある子どもは、周囲から失敗や苦手を指摘され続けてきた経験を持つことが多く、そのまま伝えると「やっぱり自分はダメなんだ」と自己否定につながりかねません。
例えば「処理速度が遅い」と言うのではなく、「一つひとつ丁寧に確認できる力がある」「理解は深いけれど、ゆっくり進めた方が力を発揮できる」と表現を変えることで、結果をポジティブに受け止めやすくなります。
また「ここが苦手だから支援を受けよう」という伝え方よりも、「こうすれば得意をもっと伸ばせる」という視点で示すことが、本人のやる気と自信を守る鍵になります。
保護者が結果を受け止めるときの注意点
保護者が検査結果を聞くときには「数値の高さ・低さ」にとらわれ過ぎないことが重要です。
たとえばIQの合計が平均より低かったとしても、それは「全体的に能力が不足している」という意味ではなく、「一部の認知機能に課題がある」ことを示している場合が多いのです。
注意すべきは「わが子の可能性を狭めてしまう言葉」を避けることです。
「この数値だから大学は無理だろう」と決めつけてしまうと、子ども自身が挑戦する前から諦めてしまいます。
検査は将来の選択肢を狭めるためではなく、進学や就労に向けた環境調整を考えるための情報です。
保護者が「どんな工夫をすれば力を発揮できるのか」という視点を持つことで、子どもの自己肯定感と意欲を支えることができます。
「ラベルを貼る」不安と「支援に活かす」ためのバランス
WAISの結果を学校や職場に伝えるかどうかは、多くの家庭にとって悩ましい問題です。
検査結果を提示すると「発達障害」というラベルが先行してしまうのではないかという不安がある一方で、結果を共有しなければ必要な支援が受けられないこともあります。
大切なのは「結果をそのままラベルとして提示する」のではなく、「支援に必要な情報だけを選んで伝える」ことです。
例えば「処理速度が遅いため、試験時間を少し長めにしてもらえると力を発揮できる」といった具体的な配慮を求める形で活用すると、本人の特性を尊重しながら支援につなげられます。
また、結果の共有については学校・職場・支援機関とよく相談し、本人の同意を得ながら段階的に進めることが望ましいです。
WAISは「制限の証明」ではなく「適切な環境を整える根拠」であることを、周囲も本人も理解していくことが支援の第一歩となります。
制度的な活用と支援のつながり
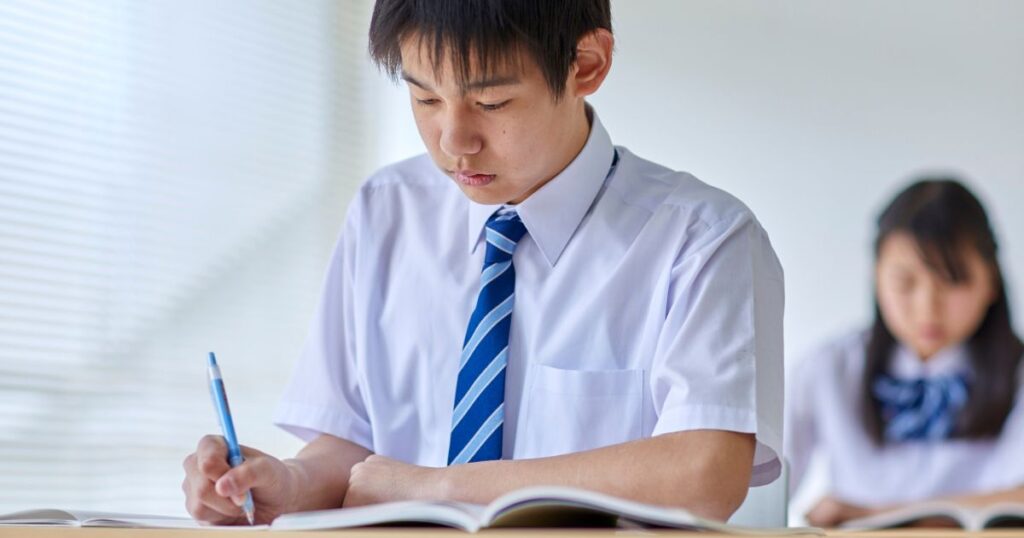
試験や学校生活での合理的配慮への活用
WAISの結果は、学校教育における「合理的配慮」を検討する際に重要な資料となります。
具体的には、定期試験や入学試験における 試験時間の延長、問題文の拡大印刷、読み上げ支援 などを申請する根拠として活用されます。
教育委員会や大学入試センターに配慮を申し出る場合、医師の診断書や心理検査の結果が求められることが多く、その一部としてWAISのプロファイルが提出されるケースがあります。
また、特別支援教育の場では「学習の困難が能力不足ではなく、特定の認知機能に起因すること」を客観的に示す資料として役立ちます。
これにより教師側も「努力不足」と誤解せず、子どもの特性に合わせた指導や教材の工夫を行いやすくなります。
職場で配慮を受けるための活用方法
就労の場面でも、WAISは「合理的配慮を検討するための情報」として利用できます。
例えば、処理速度が低い場合に「業務量を調整する」「締切に余裕を持たせる」といった配慮を求める根拠になります。
ただし、注意すべき点は「WAISの結果そのものが障害者雇用枠の認定条件になるわけではない」ということです。
雇用枠の活用には医師による診断や障害者手帳の取得が必要であり、WAISはその診断の補足資料に過ぎません。
したがって、検査結果を企業にそのまま提出するのではなく、ハローワークやジョブコーチ、支援機関を通じて「どんな配慮が必要か」を整理し、本人の同意を得て伝えることが重要です。
療育手帳や福祉サービスを利用するときの活かし方
WAISは福祉サービスを利用する際の判断材料としても用いられることがあります。
特に、知的障害の有無を確認するためにIQの数値が参照され、療育手帳の判定や福祉サービス利用の可否に影響する場合があります。
ただし、各自治体によって基準は異なり、WAISの結果だけで判定されるわけではありません。発達歴や日常生活能力の評価と総合的に判断されます。
また、放課後等デイサービスや就労移行支援などの福祉サービスでは、WAISの結果を「支援計画にどのような課題があるか」を把握する資料として活用できます。
数値はあくまで一つの指標ですが、それをもとに「どんな支援が必要か」を明確にできることで、より効果的なサポートにつながります。
まとめ│WAISは進学・就職の可能性を広げるツール
WAISは、発達障害の診断そのものを決める検査ではなく、本人の得意・不得意を客観的に可視化するための大切なツールです。
WISCからWAISへと移行する時期は、学習の基盤づくりから進学や就職といった将来の選択へと視点を広げていく重要な段階でもあります。
検査結果を正しく読み解けば、「なぜ勉強についていけないのか」「どのような配慮があれば力を発揮できるのか」が明確になります。
それは学校での合理的配慮の申請や、受験対策、さらには就労支援や職場での環境調整にも直結します。
大切なのは、数値の高低で可能性を狭めることではなく、「どの環境なら強みを活かせるか」を見極めることです。WAISは本人や家庭にとっての“未来の地図”であり、適切に活用することで進学・就職の選択肢を広げ、自己肯定感を保ちながら成長を支える指針となります。
専門家と一緒に進学・就職への道を考えてみませんか?
WAISの結果をどう解釈し、進学や就職に活かせばよいのかは、ご家庭だけで判断するのは難しいものです。
私たち煌光学園では、児童発達支援管理責任者が一人ひとりの特性をふまえて個別の支援計画を立て、学習や進路に関するご相談を承っています。
「進学に向けて何を準備すべきか知りたい」「就職に向けてWAISの結果をどう活用すればよいのか悩んでいる」など、どんな小さなことでも構いません。
ぜひ一度ご相談ください。お子さまの強みを伸ばし、安心して将来を選べるよう、専門家が一緒に伴走いたします。
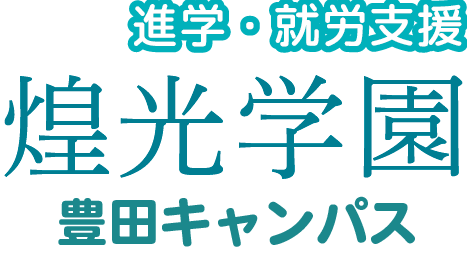
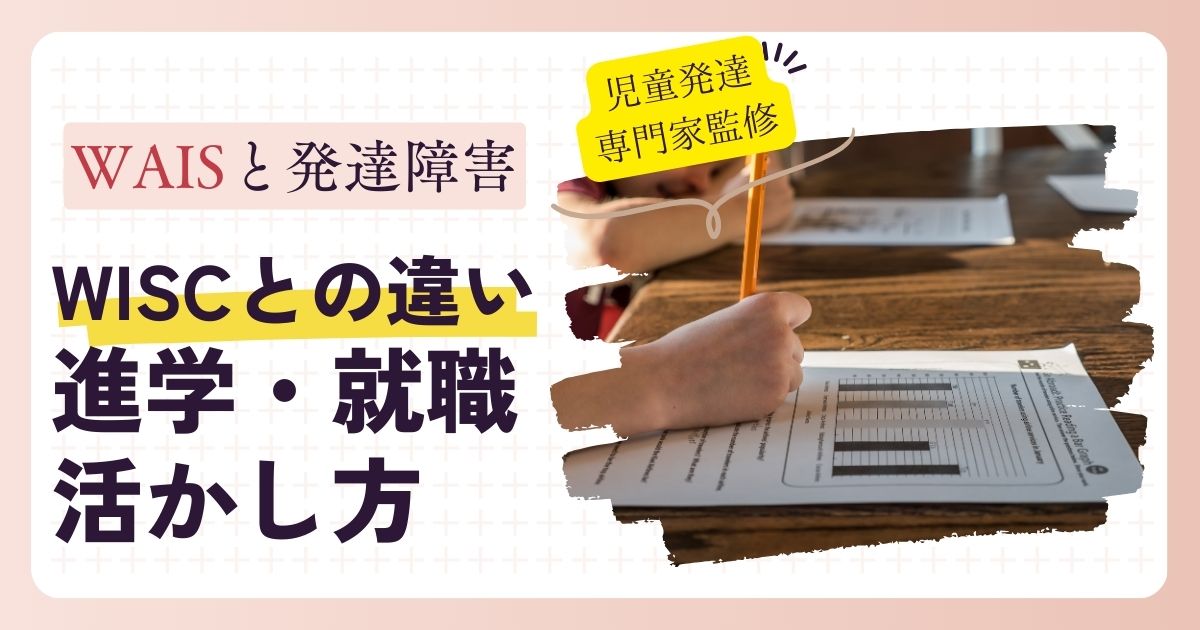
バナー-3.jpg)