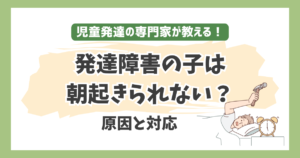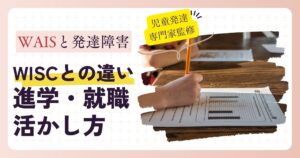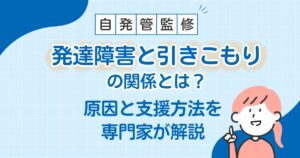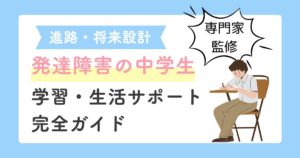「机に向かってもすぐ集中が切れる」「得意教科と苦手教科の差が大きい」──
発達障害を持つ中高生の中には、一般的な勉強法では成果が出にくい場合があります。ADHDやASDなど特性に応じた勉強方法を知り、本人が取り組みやすい環境や工夫を整えることが、成績アップや将来の進路選択につながります。
本記事では、発達障害の中高生に向けて効果的な勉強方法や環境作りのポイントを解説します。
発達障害の中高生が勉強でつまずきやすい理由
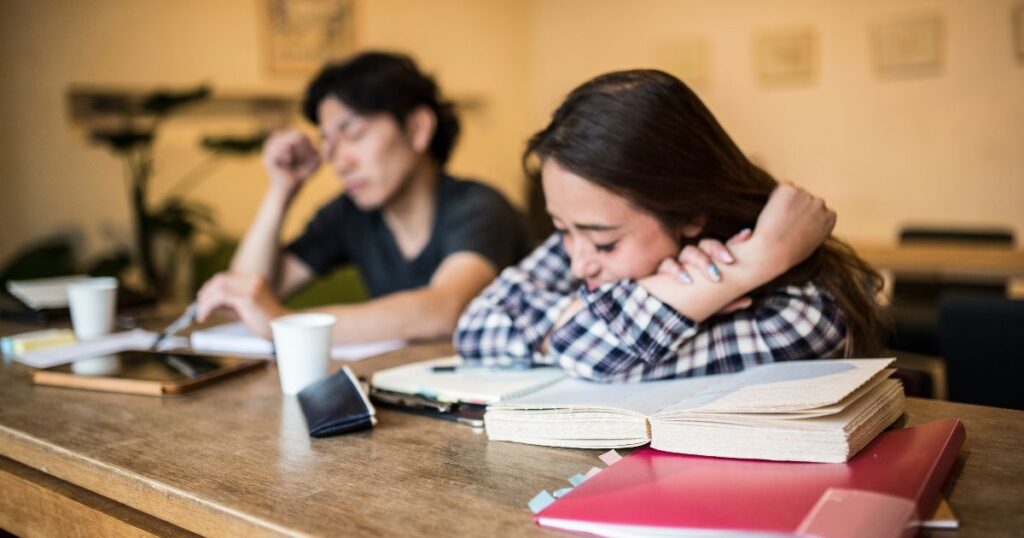
- 集中力の持続が難しい
-
ADHD(注意欠如・多動症)などの特性がある場合、授業や学習中に集中を続けることが難しい傾向があります。
周囲の物音や人の動き、掲示物などの視覚情報が気になり、学習内容に意識を向け続けるのが困難です。
また、一度集中が途切れると再び学習に戻るまでに時間がかかることも多く、結果として学習時間の割に習得量が少なくなってしまいます。 - 興味のあることへの偏りが強い
-
ASD(自閉スペクトラム症)の特性として、興味や関心のある分野に強く集中する一方、それ以外の分野にはなかなか取り組めない傾向があります。
このため、好きな教科や分野は深く学べるのに対し、苦手教科には手を付けない、課題提出が偏るといったことが起こりやすく、学力のバランスが崩れがちです。 - 見通しを立てることや計画を守るのが苦手
-
ADHDやASDの中高生は、テストや提出期限に向けて計画を立て、実行していくことが難しい場合があります。
先の予定をイメージする力が弱かったり、やるべき課題を細分化できなかったりするため、「何から手をつければいいかわからない」状態になりやすいのです。
この結果、期限直前に焦って詰め込み学習をする、課題をやり忘れるといった問題が起こります。 - 感覚過敏や環境変化への抵抗
-
発達障害の中には、音・光・匂い・触感などに対して強い敏感さを持つ「感覚過敏」の傾向が見られることがあります。
蛍光灯の明かりやクラスメイトの筆記音、教室の匂いなどが気になってしまい、集中を妨げる要因になります。
また、通学先や座席の変更など環境の変化に強い不安を感じることもあり、新しい勉強環境に馴染むまでに時間がかかることがあります。
こうした環境要因が整っていないと、本来の学習能力を発揮しづらくなります。
勉強方法を工夫する前に知っておきたい特性
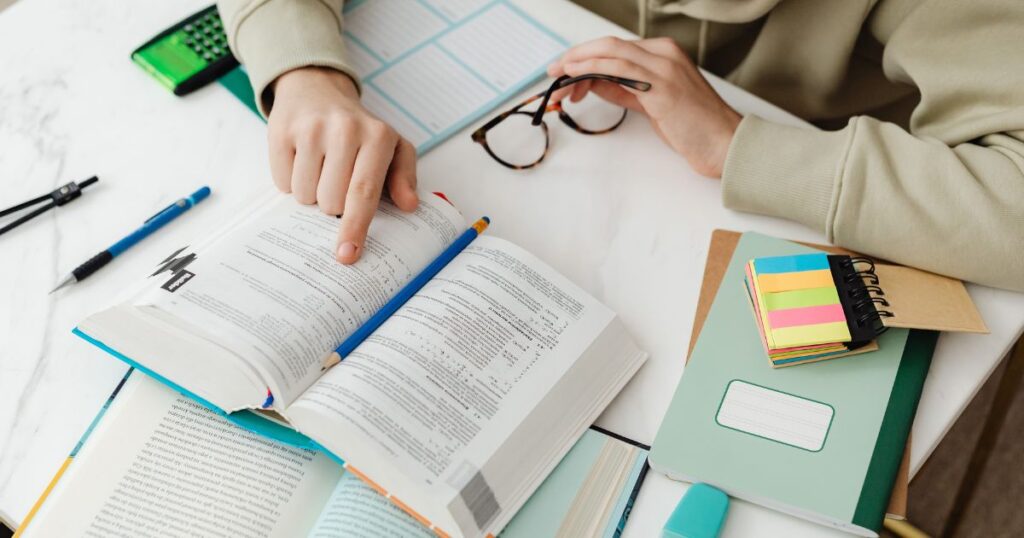
ADHD(注意欠如・多動症)の特徴と学習面での課題
ADHDの特性には、大きく「不注意」「多動性」「衝動性」があります。
不注意の傾向が強い場合は、板書の一部を書き漏らす、問題文を最後まで読まずに解答するなど、うっかりミスが目立ちます。
多動性が強いと、じっと座って学習することが苦痛に感じられ、席を立つ・姿勢を崩すなど学習態度が続かないことがあります。
また、衝動性によって、順序立てて考える前に答えを急ぐ、思いついた行動をすぐにしてしまうといったケースもあります。
こうした特性は、集中を必要とする読解や計算、時間管理が求められる課題で特に影響しやすく、成績や学習習慣の定着に影響を与えます。
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴と学習面での課題
ASDには「こだわりの強さ」「対人コミュニケーションの難しさ」「感覚の偏り」などの特性があります。
学習面では、指示が曖昧だと理解しにくく、作業の順序や方法が変わると混乱しやすい傾向があります。
好きな分野には深く集中できますが、興味がない分野への取り組みは極端に遅れがちです。
また、グループワークやディスカッションなど他者とのやりとりが伴う学習活動では、発言のタイミングや相手の意図の読み取りに苦戦することがあります。
これらは学校の授業進行や課題提出のペースに影響します。
併存するケース(LD・不安障害など)への配慮
発達障害は、ADHDやASDと学習障害(LD:読み書き・計算の困難)や、不安障害などが併存することも珍しくありません。
たとえばLDがある場合、理解力はあっても読む・書く・計算する速度が極端に遅く、時間内に課題を終えられないことがあります。不安障害が強い場合は、テストや人前での発表に強い緊張を感じ、実力を発揮できないことがあります。
こうした併存の有無によっても、効果的な勉強法や支援の形は変わります。そのため、本人の特性だけでなく併存症状の有無を含めた全体像を把握することが、勉強方法を選ぶ上での重要な前提となります。
ADHDの中高生に効果的な勉強方法
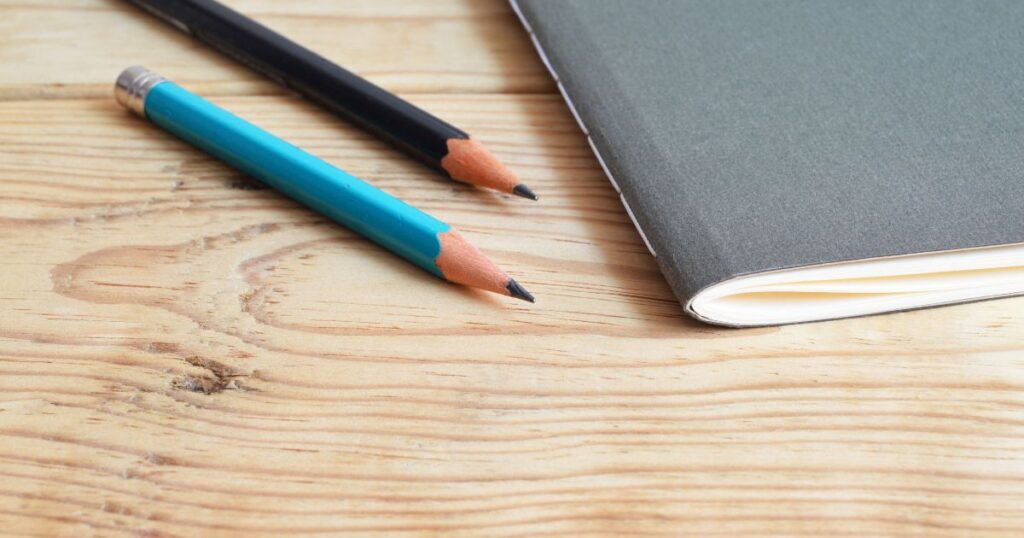
短時間集中×小休憩のサイクル学習
ADHDの特性として、長時間の集中が続きにくいことが挙げられます。
そのため「25分学習+5分休憩」など、短時間で区切るポモドーロ・テクニックのようなサイクル学習が有効です。
短時間の学習なら集中しやすく、休憩で気分を切り替えやすくなります。休憩中はスマホやゲームではなく、軽いストレッチや水分補給など頭をリセットできる行動がおすすめです。
ポモドーロタイマーを取り入れる場合は、ポモドーロタイマー用のアプリを使用したり、下記のような動画を取り入れたりするとよいでしょう。
また、見通しを立てるため、事前に
・何の教科を(または何のワーク)
・何セット(25分学習+5分休憩)やるのか
を事前に本人と決めておくことも重要です。
iOS版のポモドーロタイマーアプリ↓
YouTubeを流すだけでポモドーロタイマーとして使える動画↓
※音が出ますので感覚過敏の方には非推奨です
動きや変化を取り入れた学習(カード、タブレット活用)
じっと座って教科書を読むだけでは集中が続かない場合、動きや視覚的な変化を取り入れると効果的です。
例えば英単語をカードでめくりながら覚える、タブレットでクイズ形式の問題を解く、図や動画を交えて学習するなど、アクティブな方法が集中を保ちます。さらに、カードの順番を変える、問題形式を入れ替えるなど小さな変化を加えることで飽きにくくなります。
学習環境のノイズコントロール(席の配置、掲示物削減)
外部刺激に注意がそれやすいADHDの生徒は、環境調整が集中力維持の鍵です。
教室や自宅では、窓際や人の出入りが多い場所を避け、視界に入る情報を最小限にすることが効果的です。
机周りの掲示物やカラフルな小物は減らし、シンプルな環境に整えることで、必要な課題に意識を向けやすくなります。パーテーションで仕切るのも有効な方法です。
即時フィードバックと達成感を得られる仕組み
ADHDの生徒は「すぐに結果や反応が得られる」状況でやる気が高まりやすい傾向があります。
学習内容を細かく区切り、終わるたびに「できた!」と感じられるフィードバックを与えることが重要です。
例えば、
・プリント1枚ごとに丸付けをする
・小テストで合格スタンプを押す
・進捗を見える化した表に色を塗る、など
達成感を実感できる仕組みを取り入れると、継続意欲が高まります。
ASDの中高生に効果的な勉強方法

明確で視覚的な学習スケジュール
ASDの特性として、曖昧な指示や予定変更が苦手という傾向があります。
そのため、勉強の順序や内容を「何を・いつ・どのくらい」行うかを明確にし、カレンダーやホワイトボード、アプリなどで視覚化すると安心して取り組めます。
色分けやアイコンを使うとさらにわかりやすくなり、学習の見通しが立ちやすくなります。
手順やルールを固定化した勉強手法
学習の進め方を毎回変えるよりも、一定の手順やルールを固定化すると安心感が生まれ、集中しやすくなります。
例えば「教科書を読む→例題を解く→練習問題→答え合わせ」の流れを毎回同じにする、ノートの書き方を統一するなどです。
固定化は学習効率を高めるだけでなく、「今日はどう進めよう」という迷いを減らし、学習時間のロスを防ぎます。
得意分野を学習全体に活かす
ASDの中高生は特定分野への集中力や記憶力が高い場合があります。
その得意分野を他教科の学習にも活用することで、学びやすさが向上します。
例えば理科が得意なら、数学の関数を理科実験のデータ分析と結びつけて学ぶ、歴史の年号を好きなキャラクターや物語と関連付けるなど、興味を勉強の入口にすることでモチベーションを高められます。
見通しを立てやすくするチェックリストやタイマー活用
「あとどのくらいで終わるか」がわかると、集中しやすくなります。
学習内容を細かいステップに分けてチェックリストにし、終わったらチェックを入れることで達成感を得られます。
また、タイマーを使って「あと5分で終了」と視覚的・聴覚的に知らせることで、時間の感覚がつかみやすくなります。
これにより、学習の途中離脱やダラダラ勉強の防止につながります。
ADHD・ASDに共通する学習環境づくりのポイント

- 静かで落ち着ける場所を確保
-
発達障害のある中高生が集中して学習するためには、外部刺激を最小限に抑えた環境が必要です。
人の出入りが少なく、物音や視覚的な情報が少ない場所を選びましょう。
自宅の場合はリビングよりも個室や間仕切りを使ったスペースが適しています。
机周りは整理整頓し、学習に必要な物以外は置かないことで、集中が途切れにくくなります。 - ICT教材や音声読み上げなどの補助ツール利用
-
タブレット学習や音声読み上げ機能、拡大表示などのICTツールは、特性による学習のしづらさを補う効果があります。
例えば文章読解が苦手な場合は音声読み上げを活用し、漢字練習には筆順アニメーションを取り入れるといった具合に、本人の苦手を補えるツールを選びましょう。
これにより、学習効率を上げると同時に、自信を持って取り組めるようになります。 - ご褒美や達成感を可視化する仕組み
-
学習のモチベーション維持には「達成感」が不可欠です。
勉強の進み具合をチェックリストやカレンダーに記録し、終わったらシールを貼る、色を塗るなど、目で見て達成度を確認できる形にしましょう。
また、一定の目標を達成したらご褒美を与える仕組みを作ると、学習意欲の継続につながります。 - 保護者・学校・塾との情報共有
-
発達障害のある中高生が安定して学習を続けるためには、家庭と学校、塾など学習に関わるすべての人が連携することが大切です。
家庭では学習状況や本人の様子を記録し、学校や塾に伝えることで、課題や指導方法を統一できます。
また、特性や得意・不得意を共有しておくことで、どの場面でも一貫性のある支援が可能になります。
本人のやる気を引き出す工夫

興味関心を勉強内容に結びつける
発達障害のある中高生は、興味のある分野に強い集中力を発揮する一方で、それ以外にはなかなか取り組めない傾向があります。
そこで、好きなテーマや趣味と勉強内容を関連付けることで、学習のハードルを下げられます。
たとえば、鉄道が好きな子なら地理や物理を鉄道の構造や運行に結びつける、ゲームが好きな子なら数学の確率や英語のセリフを題材にするなど、学びの入口を広げる工夫が効果的です。
成功体験を積み重ねて自己肯定感を高める
小さな達成でも「できた!」という感覚を重ねることで、自信と意欲が育ちます。
難易度の低い問題から始めて少しずつレベルを上げる、短い時間で終わる課題を設定するなど、成功体験を意識的に組み込みましょう。
特に発達障害のある生徒は、失敗経験が積み重なるとモチベーションが下がりやすいため、最初のステップは確実にクリアできる設定にすることが重要です。
学習記録をつけて成長を実感させる
日々の学習内容や成果を記録し、過去と比較できるようにすることで、本人が成長を実感できます。
ノートやアプリ、チェック表など、見やすくて継続しやすい形式を選びましょう。
「1か月前より計算が速くなった」「前回よりテストの点数が上がった」など具体的に数値や時間で確認できる形にすると、次の学習へのモチベーションが高まります。
勉強法を定着させるためのサポート先
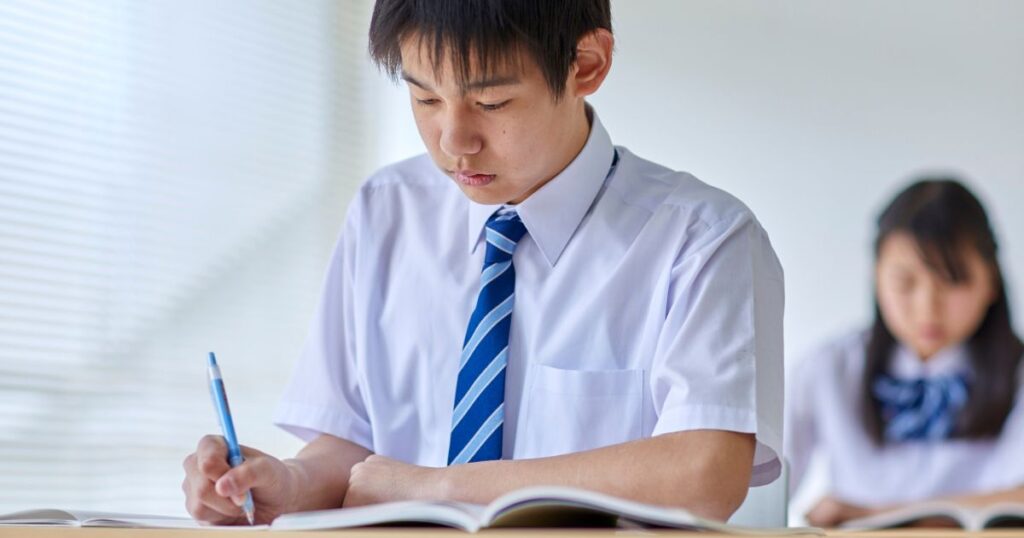
発達障害対応の個別指導塾
発達障害に理解のある個別指導塾では、特性や学習スタイルに合わせたカリキュラムを組んでくれます。
マンツーマン、または少人数での指導により、集中しやすい環境を整えやすく、学習の進捗や得意・不得意に応じて柔軟に対応してもらえます。
また、宿題や提出物の管理、テスト前の重点指導など、学習習慣の定着に向けたサポートも充実している場合があります。
煌光学園と同じ運営元であるぽかぽかステップランドは、発達支援児専門の学習塾です。
児童発達支援管理責任者が常駐し、発達支援児一人ひとりに合わせた学習法を提供しています。
ぜひ下のバナーから無料体験にお申し込みください!
放課後等デイサービス・発達支援教室
放課後等デイサービスや発達支援教室では、学習だけでなく生活面・社会性の向上も含めた総合的な支援が受けられます。
SST(ソーシャルスキルトレーニング)を通じてコミュニケーション能力や自己管理力を養うことで、学習面にも良い影響が期待できます。
宿題サポートや個別支援計画に基づいた学習支援を行っている事業所も多く、学校や家庭との連携も取りやすいのが特徴です。
家庭教師・オンライン指導
外出や環境の変化が苦手な場合、自宅で学べる家庭教師やオンライン指導が有効です。
家庭教師であれば直接対面で細やかな指導が可能で、オンラインなら全国どこからでも専門的な指導を受けられます。
ICT教材や画面共有機能を使えば、わからない部分をリアルタイムで解説してもらえるため、苦手の克服がスムーズになります。
学校との連携による支援
学校の担任や特別支援コーディネーターと連携することで、授業中や課題の取り組み方に配慮を得られる場合があります。
例えば、テスト時間の延長、別室受験、課題量の調整など、本人の負担を軽減しつつ学習を継続できるよう支援体制を整えることが可能です(学校により対応の可否は異なります)。
家庭や塾との情報共有を行えば、一貫性のある学習支援が実現し、勉強法の定着がさらに進みます。
「特性に合った学習」がカギとなる
発達障害のある中高生にとって、学習の成果は「どれだけ努力したか」だけでなく、「特性に合った勉強法を選べたか」に大きく左右されます。
ADHDには短時間集中や環境調整、ASDには明確なスケジュールや手順の固定化など、それぞれの特性に応じた工夫を取り入れることで、取り組みやすさと成果の両方が向上します。
また、本人が学びやすい環境を整え、保護者・学校・塾といった周囲のサポートを受けながら取り組むことで、学習習慣はより定着しやすくなります。
無理のない方法で継続できる仕組みを作り、成功体験を積み重ねていくことが、成績向上と将来の進路選択につながる第一歩です。
私たち煌光学園豊田キャンパスは、進学・就労準備型放課後等デイサービスとして、小学校5年生から中高生に向けて、進学に向けた学習サポートや、就職に向けた生活・スキルアップ支援をしております。
お子様の特性一人ひとりに合わせて作成したオーダーメイドの個別支援計画に基づき、将来のために必要なスキルを身につけるサポートをします。
お子様のやる気を引き出すeスポーツ設備も完備!無料体験・見学受付中です!
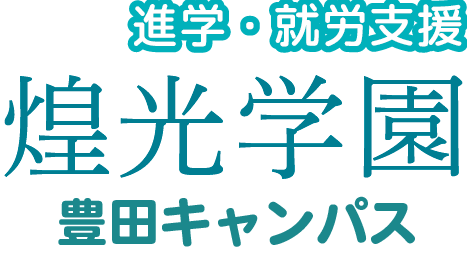

バナー-1.jpg)