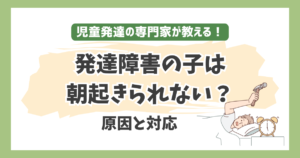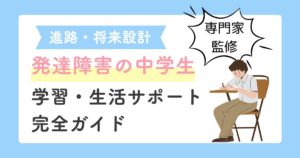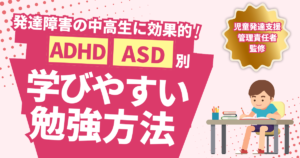「子どもが部屋から出てこない」「学校に行けず、このまま将来も引きこもってしまうのではないか」───
発達障害を持つお子さんを育てる中で、こうした不安を抱えている保護者の方は少なくありません。
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)などの特性は、学校や職場での人間関係や学習・仕事のつまずきにつながりやすく、そこから引きこもりに発展するケースもあります。
しかし、適切な支援や環境調整があれば、引きこもり状態から少しずつ社会とつながりを取り戻すことは可能です。
本記事では、発達障害と引きこもりの関係性や原因、家庭や学校でできる対応、専門機関や支援サービスの活用法を、児童発達支援管理責任者の立場から解説します。
ご家庭が孤立せず、将来に向けた安心できる一歩を踏み出すための参考になれば幸いです。
発達障害と引きこもりの関係

発達障害を持つ子どもが引きこもりに至る背景には、特性と環境とのミスマッチがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合は「相手の気持ちを読むことが難しい」「集団の暗黙ルールに合わせづらい」といった特性から、友人関係で誤解や孤立が生じやすくなります。
ADHD(注意欠如・多動症)の場合は「忘れ物が多い」「集中力のムラが激しい」「衝動的に行動してしまう」といった特徴が学校生活に影響し、叱責や失敗体験の積み重ねから自己肯定感が下がりやすいのです。
さらにLD(学習障害)では読み書きや計算に強い困難を抱えるため、学習面での挫折から「どうせ自分はできない」というあきらめにつながり、登校や社会参加を避ける傾向が見られます。
加えて、思春期は心身の変化が大きく、発達障害がある子どもはストレスを受けやすい時期です。
不安障害や抑うつ症状といった二次障害を併発するケースも多く、結果として部屋に閉じこもる行動が強まってしまいます。
発達障害と引きこもりは「本人の弱さ」ではなく、特性を理解されない環境やサポート不足によって引き起こされる現象であることを理解することが大切です。
ASD・ADHD・LDなどの特性と引きこもりやすさ
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもは、人との距離感やコミュニケーションが独特で、集団の中で孤立しやすい傾向があります。
例えば「空気が読めない」と誤解されたり、相手の気持ちに共感しづらいことから、仲間外れやいじめの対象になってしまうことがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもは、不注意や衝動性、多動性が強く現れることで、授業中に叱られる機会が多くなり、自己肯定感を失いやすいのが特徴です。
失敗体験の積み重ねは「どうせ自分はダメだ」という気持ちを強め、外の世界から距離を取る要因になります。
LD(学習障害)の場合は読み書きや計算の困難が学業不振につながり、「勉強についていけない自分は居場所がない」と感じやすくなります。
これらの特性が重なると、学校や社会に適応できない感覚が強まり、引きこもりへと発展するリスクが高まります。
思春期に現れる二次障害(うつ・不安障害など)
発達障害のある子どもは、思春期に入ると「自分は周りと違う」という自覚が強まり、ストレスや不安を抱えやすくなります。
その結果、うつ病や不安障害、強迫性障害などの二次障害を発症することが少なくありません。
例えば、学校に行く準備をするだけで動悸や吐き気が起こる、夜眠れなくなる、気分の落ち込みが続くといった症状が現れます。
二次障害が進行すると、学校や社会生活への参加がますます難しくなり、引きこもりが固定化してしまう危険性があります。
重要なのは、これらの症状を「怠けている」と誤解せず、医療やカウンセリングなど専門的な支援が必要なサインと捉えることです。
学校生活や人間関係でつまずきやすいポイント
学校は発達障害のある子どもにとって挑戦の連続です。
授業のペースが合わない、集団行動のルールを理解しにくい、休み時間の人間関係で孤立するなど、日常的に小さな失敗や不安が積み重なります。
特に中学・高校では学習内容が高度になり、友人関係も複雑化するため、つまずきが表面化しやすくなります。
また、教師やクラスメイトからの誤解や偏見によって傷つけられることもあり、「学校は自分の居場所ではない」と感じるきっかけとなります。
こうした経験が重なると登校を拒否し、そのまま引きこもりにつながるケースが多く見られます。
学校でのつまずきを早期に把握し、本人の得意な部分を活かせる環境づくりが欠かせません。
引きこもりになる原因・きっかけ

発達障害を持つ子どもが引きこもりに至る背景には、いくつかの典型的なきっかけがあります。
それは単一の出来事ではなく、学校や家庭、社会生活での「つまずき」が重なり合い、徐々に外の世界から距離を取る形で引きこもりへと発展するケースが多いのです。
不登校・いじめからの孤立
発達障害のある子どもは、集団生活で誤解を受けやすく、いじめやからかいの対象になりやすい傾向があります。
友人関係でのトラブルや居場所のなさは学校への不安を高め、「行きたいけれど行けない」という不登校につながります。
欠席が続くことで学習の遅れや人間関係の断絶が進み、結果的に自室に閉じこもる生活習慣が固定化してしまうことも少なくありません。
学業不振や進路の挫折
読み書きの困難や集中力のムラといった発達特性が、学業不振につながることがあります。
周囲と比べて成績が伸びない、受験で希望校に進めないなどの挫折体験は大きな自己否定感を生み、「どうせ頑張っても無理だ」と外界との関わりを避ける原因になります。
また、進路選択の場面で選択肢が狭まり「将来が見えない」と感じたとき、引きこもりという形で現実から距離を取るケースもあります。
就労やアルバイトでの失敗体験
高校生以降になると、アルバイトや就労の経験が始まります。
しかし、指示の理解や時間管理、人間関係の調整が難しい場合、叱責やトラブルを繰り返しやすく、早期離職につながることがあります。
その失敗体験が「社会で働けない自分」という否定的な自己イメージを強め、再挑戦への意欲を削いでしまうのです。このような経験が積み重なると、再び外に出る勇気を持てず、引きこもりが長期化することがあります。
家庭・学校・支援機関ができる対応

発達障害がある子どもが引きこもりに至った場合、家庭だけで解決しようとするのは大きな負担となり、親子関係の悪化につながることもあります。大切なのは、家庭・学校・医療・福祉が連携しながら支援の輪を広げることです。
子どもにとって安心できる環境を整え、段階的に社会とのつながりを取り戻すための工夫が必要です。
家庭での接し方と環境調整
家庭では「引きこもっている状態を責めない」ことが第一歩です。
本人の気持ちを否定せず、「あなたの存在を大切に思っている」というメッセージを伝えることが安心感につながります。
例えば、無理に外出を促すのではなく、好きな趣味や得意な活動を一緒に楽しむことから関わりを深めると効果的です。
生活リズムを整えるために、朝の挨拶や食事を一緒にとるなど、小さな習慣を積み重ねることも支援になります。
また、刺激の少ない部屋作りや、本人が安心して過ごせる空間を整えることも重要です。
学校での配慮と支援体制
学校は、本人にとって「戻りたい居場所」になるかどうかが大きなポイントです。
出席日数や課題提出に柔軟な対応をしたり、別室登校や段階的な復帰プランを用意するなどの工夫が有効です。
担任だけでなく、特別支援教育コーディネーターやスクールカウンセラーが関わることで、より専門的な支援が受けられます。
家庭と学校の連携を密にし、子どもの状態に合わせた学び方や居場所づくりを進めることが、再登校や学習意欲の回復につながります。
医療・カウンセリングによる支援
うつや不安障害などの二次障害が見られる場合、早めに医療機関や専門カウンセラーにつなげることが大切です。
精神科・心療内科・発達外来などで診断や治療を受けることで、適切な薬物療法や心理療法が受けられます。
また、臨床心理士や公認心理師によるカウンセリングは、本人が安心して気持ちを言葉にできる場となり、孤立感の軽減につながります。
福祉サービス・就労支援の活用方法
発達障害の子どもや若者の引きこもり支援には、地域の福祉サービスを活用することが欠かせません。
放課後等デイサービスや発達障害者支援センターでは、ソーシャルスキルトレーニング(SST)や生活習慣のサポートが受けられます。
高校卒業後は、就労移行支援や就労継続支援A・B型事業所を利用し、段階的に働く経験を積むことができます。
また、ひきこもり地域支援センターや若者サポートステーションといった地域資源も、外との接点を取り戻すきっかけになります。支援をつなぎ合わせることで、本人に合った将来設計が可能になります。
引きこもりから回復するステップ

引きこもりからの回復は、一気に社会参加を目指すのではなく、小さな一歩を積み重ねることが大切です。
本人のペースを尊重しながら「安心できる場 → 新しい体験 → 社会参加」という段階を踏むことで、無理のない回復が可能になります。
小さな外出や日常生活のリズムづくり
まずは生活リズムを整えることから始めましょう。
朝起きてカーテンを開ける、家族と一緒に食事をする、といった日常の習慣が外に出る準備につながります。
次のステップとしては、コンビニや図書館に短時間立ち寄るなど「成功体験を積みやすい外出」を取り入れるのが効果的です。
小さな成功を繰り返すことで「外に出られた」という自信が芽生え、次の行動につながります。
学び直しや通信制高校・サポート校の利用
学校復帰が難しい場合でも、学びを止めない選択肢があります。
通信制高校やサポート校は、自分のペースで学べる環境が整っており、不登校や引きこもりを経験した生徒を受け入れてきた実績があります。
オンライン授業や少人数クラスなど柔軟な仕組みがあるため、安心して学び直すことができます。学習を続けることは、将来の進路や自己肯定感の回復に直結します。
就労支援や職場体験へのステップアップ
外出や学習が少しずつ安定してきたら、次は社会との接点を広げる段階です。
就労移行支援事業所や若者サポートステーションでは、基礎的な生活スキルや職業訓練を受けることができ、安心して就労体験に取り組めます。
短時間の職場体験やボランティア活動から始めることで、無理なく「社会に参加できる自分」を実感できます。最初の仕事での失敗は誰にでもあるもの。サポートを受けながら少しずつ挑戦を重ねることが、将来の自立につながります。
回復した事例・体験談

引きこもりからの回復は決して一朝一夕ではありませんが、適切な支援と環境が整えば少しずつ社会とのつながりを取り戻すことができます。
ここでは実際のケースを参考に、どのように回復していったのかを紹介します。
本人の特性を理解した支援で社会復帰した例
中学生の頃から不登校になり、3年間引きこもり生活を送っていたASDのある男子生徒がいました。
家庭では「無理に学校に行かせない」ことを大切にしつつ、地域の発達障害者支援センターと連携し、週1回のカウンセリングから外との接点を再開。
次第に放課後等デイサービスでの活動に参加できるようになり、高校進学時には通信制高校へ。
少人数クラスや個別指導のサポートを受けながら勉強を続け、現在は就労移行支援を利用しながら一般企業への就職を目指しています。
このケースでは、本人の特性に合った学びと安心できる居場所が回復の大きな支えになりました。
家族が孤立を防ぎ共に成長した例
ADHDの特性が強く、友人関係のトラブルから引きこもりになった女子高生のケースです。
当初、母親は「なんとか学校に戻さなければ」と焦っていましたが、保護者同士の親の会に参加することで「焦らなくてもいい」という気持ちを持てるようになりました。
その後、家庭では本人の好きなイラスト活動を尊重し、成果をSNSで発信することで外とのつながりを持ち始めました。
家族も支援機関と連携し、進学よりも本人の得意を活かす就労支援に舵を切ることで、本人の自己肯定感が徐々に回復。
現在はイラストを活かしたデザイン系の仕事に就いています。このケースからは、家族自身が孤立せず支援を受けることの重要性がわかります。
相談できる専門機関・地域資源

引きこもりが長期化すると、家庭だけで支えることは難しくなります。
そんなときは、専門機関や地域の支援資源を活用することが大切です。外部の専門家とつながることで、親子が孤立せず、回復への具体的なステップを見出しやすくなります。
発達障害者支援センター
各都道府県に設置されている公的な支援機関で、発達障害のある本人や家族が無料で相談できます。
医療・教育・福祉とつながる窓口としての役割を持ち、療育や就労支援への橋渡しも行っています。「どこに相談すればいいかわからない」というときに、まず頼れる場所です。
ひきこもり地域支援センター
厚生労働省の方針に基づき全国に設置されているセンターで、引きこもりに特化した相談窓口です。
臨床心理士やソーシャルワーカーが在籍し、本人や家族の相談を受け付けています。家庭訪問やグループ活動を通して、外に出るきっかけづくりを支援してくれるのが特徴です。
児童発達支援・放課後等デイサービス
18歳までの子どもを対象に、日常生活のサポートやソーシャルスキルトレーニング(SST)を行う場です。
安心できる環境の中で、同世代の仲間と過ごす体験を通して社会性を養うことができます。中高生向けの事業所も増えており、学校以外の居場所として重要な役割を果たしています。
親の会・ピアサポート
同じような経験を持つ親や当事者同士でつながることも大きな支えになります。
親の会やピアサポート団体では、体験を共有することで孤独感が軽減され、「うちだけではない」と感じられる安心感が得られます。
また、実際に回復につながった具体的な工夫を知ることもできます。
将来の生活設計と就労支援の選択肢

引きこもりから回復しても、「この先、どのように生活していけるのか」という不安は尽きません。
特に発達障害のある若者にとっては、進学や就職のハードルが高く感じられることも多いです。
そこで重要なのが、長期的な生活設計と就労支援の選択肢を知っておくことです。将来の見通しが持てるだけで、本人も家族も安心感を得られます。
特例子会社や障害者雇用枠での就労
企業には、一定割合の障害者を雇用する義務があります。
その中で、発達障害のある人が安心して働けるように設けられたのが「障害者雇用枠」や「特例子会社」です。
配慮のある職場環境やサポート体制が整っており、自分の得意を活かした働き方が可能です。初めての社会参加として利用しやすい選択肢と言えるでしょう。
就労移行支援やA型・B型事業所の活用
福祉サービスとして提供される就労移行支援事業所では、働くための基礎スキルや職業訓練を受けられます。
また、就労継続支援A型事業所では雇用契約を結びながら働く経験が積め、B型事業所ではより柔軟に自分のペースで作業に取り組めます。
段階的に社会参加を広げられる仕組みが整っているため、引きこもり経験者が安心して挑戦できる環境です。
進学・就職準備型煌光学園豊田キャンパスでは、施設内にグループ法人が運営している就労継続支援A型・B型キラキラがあります。
キラキラで働く人々を見たり、職場体験に訪れたりすることで、自分の適正や将来で働くビジョンを持ちやすいです。
福祉制度を活用した安心できる生活基盤づくり
将来の生活を安定させるためには、障害年金や生活支援サービスなどの制度を正しく理解し、必要に応じて活用することも大切です。
経済的な不安を軽減することで、本人が社会参加に集中しやすくなります。
また、グループホームや自立生活援助といった住まいの支援も、将来的な自立を見据えるうえで有効です。
このように、学び直し → 就労支援 → 安定した生活基盤づくり という流れを意識してサポートすることで、将来の選択肢は大きく広がります。
まとめ│発達障害と引きこもり支援は「孤立させないこと」が鍵
発達障害のある子どもが引きこもりに至る背景には、特性そのものよりも「理解されないままの環境」や「失敗体験の積み重ね」があります。
不登校や学業不振、いじめ、就労のつまずきなどが引き金となり、家庭でも安心できなくなると、引きこもりは長期化しやすくなります。
しかし、支援のポイントは明確です。家庭では否定せず寄り添うこと、学校では柔軟な対応をとること、そして医療・福祉サービスとつながることが、回復への第一歩になります。小さな外出や生活リズムの調整から始め、学び直しや就労支援につなげていけば、社会との接点を少しずつ取り戻せます。
大切なのは、本人も家族も「孤立しない」ことです。相談できる機関や同じ経験を持つ仲間とつながることで、不安は和らぎますし、次の一歩を踏み出す勇気につながります。
発達障害と引きこもりの課題は一人で抱えるものではなく、周囲と支援を共有しながら共に乗り越えていくものです。
 児発管とおる先生
児発管とおる先生煌光学園では、不登校や引きこもりの中高生向けに進学・就職の
サポートをしています!
保護者のご相談も歓迎ですので、ぜひ来てくださいね。
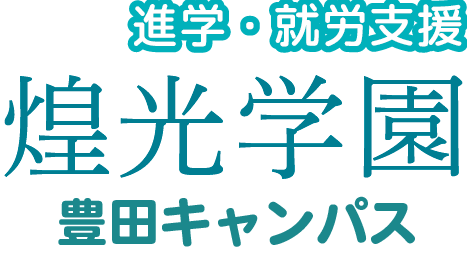
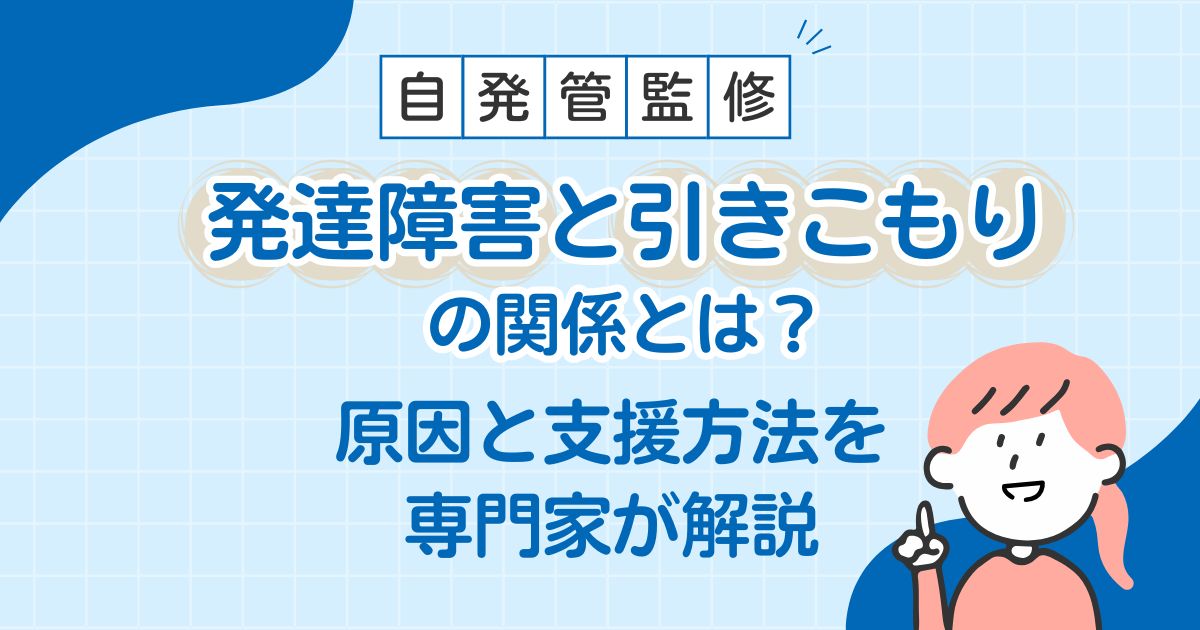
バナー-2.jpg)