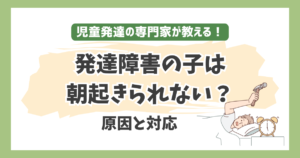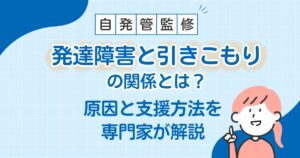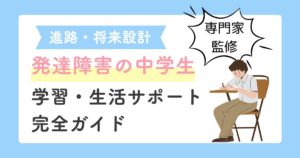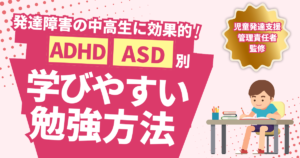「スマホをやめられない」
「課金トラブルが心配」
「SNSでの人間関係が不安」
発達障害のある子どもを育てる中で、スマホ利用に頭を悩ませている保護者は少なくありません。ASDやADHDの特性が影響し、ゲームやSNSにのめり込みやすいこともあります。
本記事では、発達障害とスマホ利用の関係、家庭でできる時間管理やルールの作り方、ペアレンタルコントロールの設定方法、課金トラブルの予防、そして学校や専門機関との連携までを解説します。
専門的な視点から「今日からできる工夫」をまとめていますので、ぜひご家庭での対応の参考にしてください。
発達障害とスマホ利用の関係
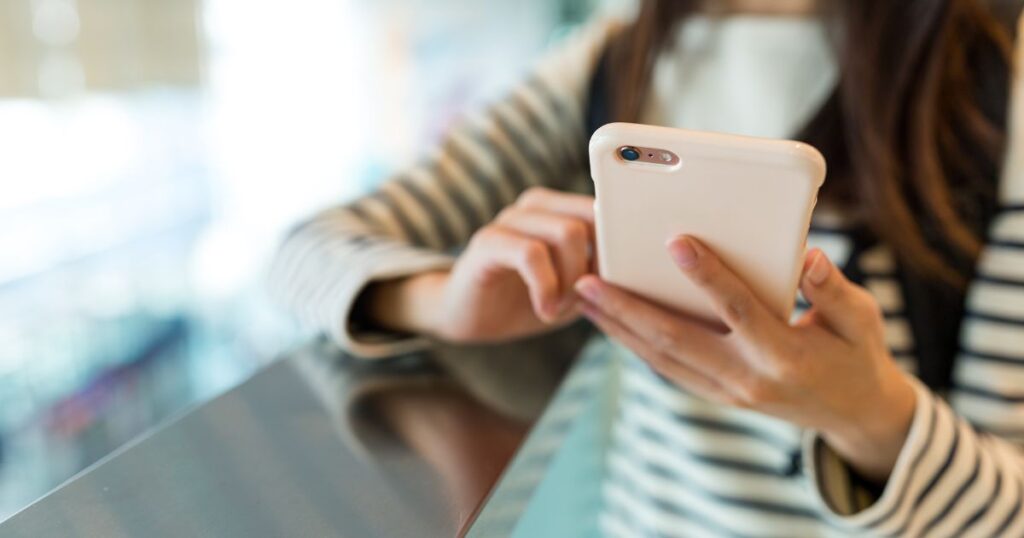
発達障害を持つ子どもは、スマホやゲームの利用に特有のリスクが生じやすい傾向があります。
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)といった特性は、デジタル機器の長時間使用や依存につながりやすい背景となります。
親が「なぜこんなにやめられないのか」と戸惑う行動も、脳の働きや特性に深く関係しています。
ここでは、代表的な特性とスマホ依存の関係について見ていきましょう。
ASD・ADHD特性とスマホ依存のリスク
ASDの子どもは、自分の関心ある世界に強いこだわりを持つ特徴があり、同じゲームや動画を繰り返し視聴することがあります。
画面の中の一貫したルールやパターンに安心感を覚えるため、スマホの利用が習慣化しやすいのです。
一方ADHDの子どもは、刺激を求めやすく、報酬がすぐ得られる活動に強く惹かれる傾向があります。
ゲームのレベルアップやSNSの通知は「すぐに得られるご褒美」として作用し、やめにくさを助長します。
また、ASDとADHDの両方の特性を併せ持つ子どもも少なくなく、依存のリスクがさらに高まるケースも見られます。これは単なる「意思の弱さ」ではなく、脳の特性に由来する自然な傾向です。
したがって、保護者は「やめさせなければ」よりも「どう環境を整えるか」という視点を持つことが大切になります。
ゲーム・SNSにハマりやすい背景(衝動性・切り替え困難・こだわり傾向)
発達障害の子どもがスマホにのめり込みやすい背景には、いくつかの特性が関わっています。
ADHDに特徴的な「衝動性」により、「あと少しだけ」という制御が難しく、時間を忘れて遊んでしまうことがあります。
また「切り替え困難さ」も大きな要因です。楽しんでいる最中に突然「やめなさい」と言われると強い反発が起こり、親子の衝突につながりやすくなります。
ASDの特性である「こだわり」も、同じゲームやSNSの世界に深く入り込む理由のひとつです。
ゲームのルールやキャラクター収集など、秩序立った世界に安心感を覚えるため、現実の活動よりもスマホの世界を優先してしまうのです。
これらの背景を理解することで、「なぜこんなにハマってしまうのか」という疑問に答えられ、対応の第一歩となります。
家庭でできる利用時間の管理方法

発達障害のある子どもは、スマホやゲームの時間を自分でコントロールするのが難しいことが多いです。
衝動性や切り替えの難しさといった特性により、「あと少し」が「気づいたら何時間も」に変わってしまうのです。
こうした場合、保護者が「やめなさい」と強制するだけでは、反発や親子関係の悪化につながります。
家庭での工夫や環境づくりが、子ども自身の成功体験を増やし、無理のない利用時間の管理につながります。
スマホやゲームをやめられない時の対応
まず大切なのは「やめるタイミングを予告する」ことです。
突然中断を迫られると、発達障害の子どもは強い不安や怒りを感じやすくなります。
「あと10分で終わりにしよう」「このステージが終わったら休憩ね」と前もって伝えるだけで、切り替えやすくなるケースがあります。
また「やめた後の行動」を具体的に示すのも効果的です。
「終わったら一緒におやつにしよう」「この後は散歩に行こう」といった見通しを持たせることで、次の行動へ移りやすくなります。
さらに、やめられた時には「よく切り替えできたね」と肯定的な言葉をかけ、達成感を積み重ねていくことが大切です。
タイマー・スクリーンタイム機能・アプリ制限の活用
家庭での工夫に加え、テクノロジーの力を活用するのも有効です。
キッチンタイマーや目覚まし時計など、外部のタイマーを利用すると「時間が来たから終わり」というルールを受け入れやすくなります。
また、iPhoneやAndroidには「スクリーンタイム」や「デジタルウェルビーイング」といった機能があり、アプリごとの利用時間を制限できます。
特定のアプリが一定時間を超えると自動的にロックされる仕組みは、子どもにとっても「ルールだから仕方ない」と納得しやすいものです。
さらに保護者がパスコードを設定することで、無断延長を防ぐことができます。
こうしたツールを使うことで、家庭内の「やめなさい」という声かけが減り、親子の摩擦を和らげることにもつながります。
無理なく守れるルール設定の工夫
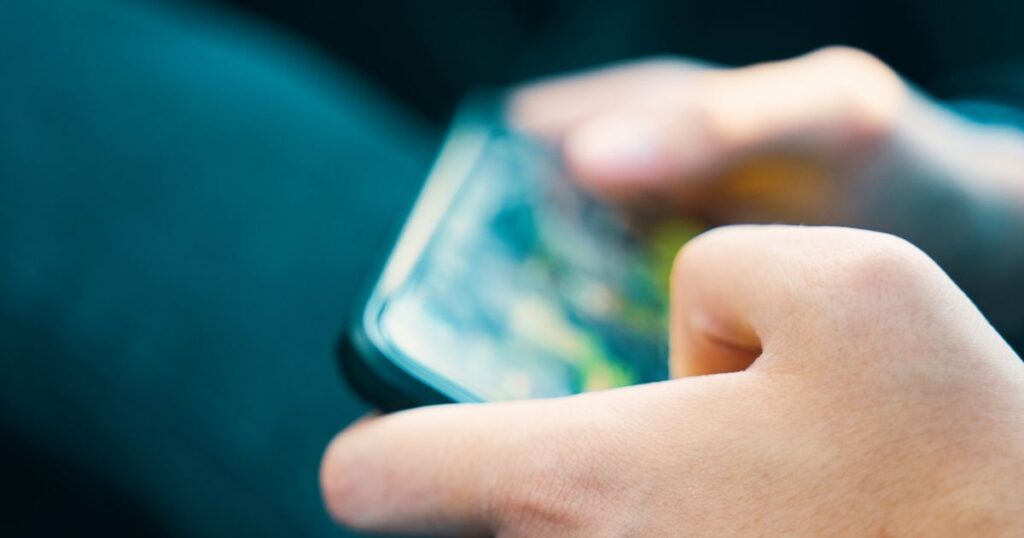
スマホの利用ルールは、単に「禁止する」だけでは長続きしません。
発達障害のある子どもにとっては、時間の感覚や衝動のコントロールが難しいため、強い禁止はかえって反発や隠れての使用につながることもあります。
大切なのは、子どもが納得しやすく、家庭で自然に守れるルールを作ることです。
「何時以降は使用禁止」など具体的なルールの決め方
ルールはあいまいにせず、具体的に決めることが大切です。
「夜は早く寝よう」よりも「21時以降はリビングで充電して、翌朝まで使わない」といった明確な形にします。
また「食事中は使わない」「宿題が終わってからゲームをする」といった生活習慣とセットにするのも有効です。
さらに、子どもの特性に合わせた工夫も必要です。
例えば切り替えが苦手な子には「就寝30分前に音楽を聴く」など代替行動を提案するとスムーズに移行しやすくなります。家庭で実行可能なルールを少しずつ取り入れていくことで、習慣化につながります。
親子で合意形成するためのポイント(罰より仕組み化)
ルールを親が一方的に決めると、子どもは「押し付けられた」と感じやすく反発します。
そのため、話し合いの中で「どうすればうまくいくか」を一緒に考えることが大切です。
たとえば「夜更かしすると朝がつらいね。何時までなら大丈夫そう?」と子どもに意見を聞き、妥協点を見つける方法です。
また、守れなかった時に罰を与えるのではなく「仕組みで自然に守れるようにする」工夫も有効です。
リビングにしか充電器を置かない、寝室にはスマホを持ち込まないといった環境調整は、口頭で注意するより効果的です。
ルールを守れたときには「ちゃんとできたね」と肯定的に伝えることで、子どもの自信や自己肯定感を高めていけます。
ペアレンタルコントロールと安全対策

スマホ利用における最大の不安は「依存」だけでなく、「外部とのトラブル」や「課金リスク」です。
特に発達障害のある子どもは、危険性を予測したり、相手の意図を読み取ったりするのが難しい場合があり、知らない人との交流や過剰な利用に巻き込まれるリスクが高まります。
保護者によるペアレンタルコントロール機能の活用は、安心して子どもにスマホを持たせるための大切な支えになります。
iPhone・Androidでの利用制限の設定方法
iPhoneには「スクリーンタイム」、Androidには「ファミリーリンク」や「デジタルウェルビーイング」といった機能が標準搭載されています。
これらを使うと、アプリごとの利用時間の制限や、使用できる時間帯の指定が可能です。たとえば「22時から翌朝7時まではアプリを使えない」と設定すれば、夜更かし防止につながります。
さらに、アプリのインストールや課金に保護者の承認を必須にする設定もできます。
これにより「知らないうちに課金していた」「勝手にアプリを入れてしまった」といったトラブルを防止できます。
発達障害の子どもにとっては「ルールだからできない」という仕組みが逆に安心感につながる場合も多く、親子で衝突せずに管理できるのが大きな利点です。
LINE・SNSの安全設定と知らない人とのトラブル防止
SNSやLINEは友人関係を広げる一方で、見知らぬ相手との接触やトラブルにつながりやすい面があります。
発達障害のある子どもは相手の意図を読み違えたり、安易に個人情報を教えてしまったりするリスクが高いことに注意が必要です。
保護者はまず「友だち追加を許可しない」「ID検索をオフにする」など、アカウントの基本設定を見直しましょう。
また、SNSの公開範囲を「友人のみ」に制限することも有効です。
さらに、知らない人からのメッセージに返信しないルールを共有し、実際に不審なメッセージを見せて具体的に指導することも役立ちます。
こうした安全対策を講じることで、子ども自身がトラブルを回避できる力を少しずつ身につけていくことが期待できます。
課金トラブルへの対応と予防

スマホ利用で特に注意したいのが、ゲームやアプリでの課金トラブルです。
発達障害のある子どもは「欲しいと思ったらすぐに行動してしまう」衝動性や、「今すぐ手に入れたい」という強い欲求を抑えにくい特性があるため、思いがけず高額課金をしてしまうことがあります。
家庭の経済面への影響はもちろん、子ども自身の自己肯定感を下げるきっかけにもなりかねません。予防と早めの対応が重要です。
購入制限・パスワード設定による課金管理
課金を防ぐためには、スマホの機能を活用した仕組みづくりが欠かせません。
- iPhoneの場合
-
「スクリーンタイム」から「コンテンツとプライバシーの制限」を設定し、アプリ購入や課金時に必ずパスワードを求めるようにできます。
- Androidの場合
-
「Googleファミリーリンク」や「Playストアの購入認証」を活用することで同様の管理が可能です。
また、クレジットカードやプリペイドカードの登録を控え、課金は保護者がその都度決済するようにするのも効果的です。
子どもに「自分では買えない仕組み」を整えることで、親子間の衝突を減らしつつ安心して利用できます。
課金トラブルが起きた際の返金・相談窓口
もし実際に高額課金が発生してしまった場合も、冷静に対応しましょう。
AppleやGoogleには返金申請の仕組みがあり、条件によっては払い戻しが認められることがあります。
購入履歴を確認し、早めに手続きを行うことが大切です。
また、クレジットカード会社への連絡や、消費生活センター(消費者ホットライン188)への相談も有効です。
発達障害の子どもの特性による行動であった場合、事情を説明すると柔軟に対応してもらえるケースもあります。
「一度失敗したからもうダメ」ではなく、適切な手段を知ることで子どもと保護者双方の不安を減らし、今後の利用ルールの見直しにもつなげることができます。
学校や専門機関との連携

家庭での工夫だけでは、スマホ利用の課題を完全に解決できないことも少なくありません。
特に発達障害のある子どもは、学校生活や人間関係に直結する問題として表れることがあり、家庭だけで抱え込むのは負担になります。
学校や専門機関と連携することで、家庭だけでは得られないサポートを受けられ、子どもの安心と成長につながります。
学校側ができるスマホ利用への関与
学校では、基本的に授業中のスマホ利用は禁止されていますが、それ以上に「生活習慣や学習態度への影響」として家庭と協力できる部分があります。
担任やスクールカウンセラーに「夜遅くまでスマホを使ってしまい、朝の登校が難しい」といった実態を共有すると、生活リズムの改善や学習支援の観点からアドバイスをもらえる場合があります。
また、学校内でもスマホの使い方に関する指導や講習会を行っているケースがあります。発達特性に配慮しながら情報モラルを学べる機会を子どもが持てるよう、学校に働きかけるのも一つの方法です。
発達支援・カウンセリングでの相談の可能性
発達支援センターや放課後等デイサービスでは、スマホ依存や利用ルールについても相談が可能です。
発達障害特性に理解のある専門職(児童発達支援管理責任者、臨床心理士、言語聴覚士など)が、家庭に合った工夫や実践的なアドバイスを行います。
また、医療機関の心療内科や小児科で相談することで、必要に応じてカウンセリングや認知行動療法といった心理的アプローチを受けられることもあります。
「スマホ利用の背景にある発達特性や不安」にまで目を向けてくれるため、ただ制限するだけでなく、本人が納得しやすい支援方法を一緒に探すことができます。
こうした専門機関との連携は、保護者が孤立せず安心して子育てを続けるうえでも大きな力になります。
スマホ以外の時間をつくる工夫
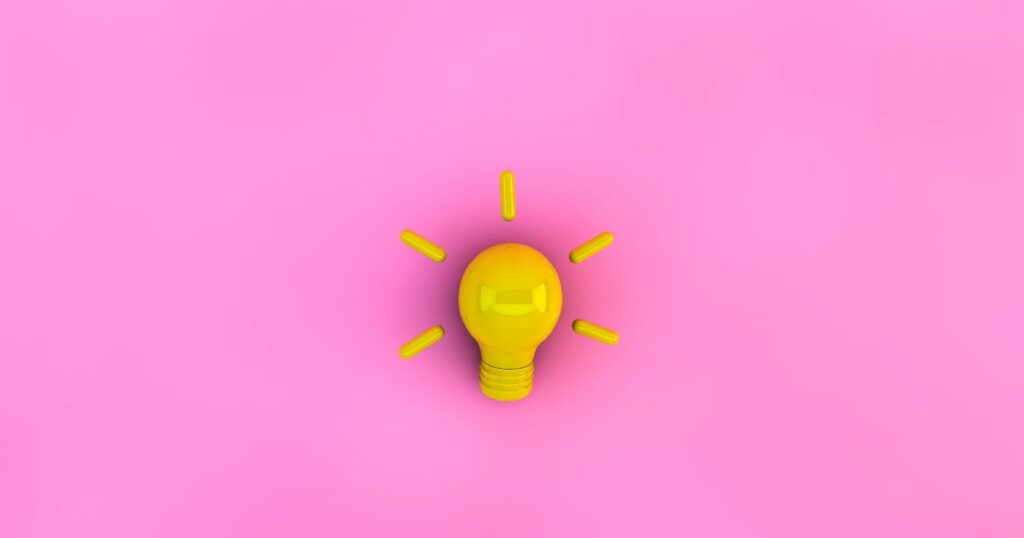
スマホの利用を減らすには、「やめなさい」と禁止するだけでは不十分です。
その代わりとなる楽しみや安心できる活動を生活の中に取り入れることが重要です。
発達障害のある子どもは、特定の活動に強く集中したり、興味関心に偏りがあることが多いため、それを肯定的に活かせる時間を設けることで、自然とスマホ以外の過ごし方にシフトできます。
趣味・運動・交流活動など代替手段
まずは子どもが興味を持てる活動を見つけましょう。絵を描く、プラモデルを作る、音楽を聴く・演奏するなど、家でできる趣味も良い選択です。
体を動かすのが得意な子にはスポーツや散歩、苦手な子でもヨガやストレッチなどリラックスにつながる活動がおすすめです。
また、同じ特性を持つ子ども同士が交流できるイベントや地域活動に参加することで、安心して人間関係を築く経験ができます。
スマホの世界に閉じこもる時間が減り、実際の体験を通して「楽しい」「落ち着く」と感じられることが、自然と利用時間の調整につながります。
家庭で実際に改善できた成功事例
実際に、ある家庭ではADHDの男の子がゲームに熱中しすぎて夜更かしが続いていましたが、家族で「夕食後はカードゲームをする」という習慣を取り入れたところ、徐々にゲーム時間が短縮されました。
ルールや駆け引きのあるカードゲームは本人の興味を引き、家族との交流も増えたことで安心感が高まったのです。
またASDの女の子の場合、スマホで動画を繰り返し見る習慣がありましたが、週に数回イラスト教室に通い始めると、自分の作品作りに集中する時間が増え、自然とスマホ利用が減少しました。
本人にとって「達成感のある活動」が増えることで、無理なく生活習慣が変わった例です。
このように、スマホ以外の選択肢を生活に組み込むことが、依存の予防にも改善にもつながります。
将来への不安と潜在的リスク

スマホ利用の問題は、今この瞬間だけでなく、将来への影響を考えるとさらに保護者の不安は大きくなります。
「このまま依存が続いたら学業は?」「大人になってもゲームばかりでは?」といった心配は、多くの家庭で共通しています。
加えて、家庭内の関係性や子どもの心の発達にも影響するため、早めに理解し、支援につなげていくことが大切です。
学力・進学・自立への影響
スマホに長時間没頭することで、学習時間や睡眠時間が削られ、学力の低下につながる可能性があります。
特に発達障害のある子どもは「一度遅れると取り戻すのが難しい」という学習上の課題を抱えやすいため、スマホ依存は進学や将来の選択肢を狭めるリスクになります。
さらに、生活習慣が乱れることで朝起きられず欠席や遅刻が増え、内申点や出席日数に影響する場合もあります。
進学後や社会に出た後も「自己管理ができない」と見られてしまう懸念もあり、早期に対応することが重要です。
親子関係の悪化と子どもの自己肯定感の低下
「早くやめなさい」「いい加減にしなさい」と繰り返すうちに、親子関係がギクシャクしてしまうことは珍しくありません。
特に発達障害のある子どもは叱責を繰り返されると「自分はダメな子だ」と感じやすく、自己肯定感が低下してしまいます。
また、親も「どうしてうちの子だけ…」と自分を責めたり、孤立感を抱えることがあります。
こうした悪循環は家庭の雰囲気を悪化させ、子どもの安心感を奪ってしまうため、単なるスマホの使いすぎ以上に深刻な課題となります。
親子双方の気持ちを守るためにも、「叱る」より「仕組みを工夫する」方向へ切り替えることが望まれます。
同じ悩みを持つ親の孤立感と共感の必要性
「うちの子だけがこんなにスマホにのめり込んでいるのではないか」と感じ、周囲に相談できずに抱え込んでしまう保護者も少なくありません。
しかし実際には、同じ悩みを持つ家庭は数多く存在します。孤立したままでは不安やストレスが募り、子どもへの対応にも影響してしまいます。
同じ課題を抱える親同士で話し合える場や、発達支援の専門家から具体的なアドバイスを受けられる機会は、気持ちを大きく支えてくれます。
「自分だけではない」と実感することが、冷静に子どもと向き合うための力につながります。
孤立感を和らげる工夫も、スマホ利用の課題を乗り越える上で欠かせない要素です。
支援につなげるためにできること

スマホ利用の課題は、家庭だけで解決しようとすると限界があります。
発達障害のある子どもの特性を踏まえた対応が必要だからこそ、学校や専門機関とつながり、客観的なサポートを得ることが大切です。
適切な支援につながることで、親子の負担が軽減され、子どもの成長を長期的に支えることができます。
学校・発達支援センター・医療機関への相談先
まず身近なのは、子どもが通っている学校です。担任やスクールカウンセラーに相談することで、生活習慣や学習態度への支援につながります。また、地域の発達支援センターでは、スマホ依存を含む生活面の困りごとについて、専門職が具体的なアドバイスを行ってくれます。
医療機関では、小児科や児童精神科・心療内科で相談可能です。必要に応じてカウンセリングや認知行動療法などを通じ、本人に合ったアプローチを提案してもらえます。早めに相談することで、依存が深刻化する前に適切な支援につなげられます。
スマホ利用と発達特性を理解した支援者につながる方法
重要なのは、スマホ依存だけでなく「発達特性」を理解している支援者と出会うことです。
発達障害に詳しい児童発達支援管理責任者や臨床心理士、発達支援を専門とする放課後等デイサービスなどでは、子どもの特性に合わせた実践的な支援が可能です。
また、保護者向けの相談会やペアレントトレーニングに参加することで、同じ課題を抱える親とつながり、実際に効果のあった工夫を知ることができます。
「孤立せず、相談できる場所がある」という安心感は、保護者にとっても子どもにとっても大きな支えになります。
支援者との連携は「子どもを管理するため」ではなく、「安心して暮らすための環境を整えること」。その視点を持つことで、親子が前向きにスマホと向き合えるようになります。
まとめ│スマホ利用と発達特性を理解し、親子で安心できる支援を
発達障害のある子どもにとって、スマホは学びや遊びのツールである一方、依存や課金トラブル、SNSでの危険など多くのリスクを伴います。
ASDやADHDの特性によって「やめられない」「切り替えられない」行動が強まることもありますが、それは決して本人の努力不足ではなく、脳の特性によるものです。
家庭でできる工夫としては、利用時間の予告やタイマー設定、スクリーンタイム機能の活用、無理のないルールづくりが効果的です。
また、趣味や交流活動などスマホ以外の楽しみを生活に取り入れることも大切です。さらに、課金制限やSNS設定といった安全対策を整えることで、安心して利用できる環境が整います。
それでも家庭だけで対応が難しい場合は、学校や発達支援センター、医療機関に相談しましょう。スマホ利用と発達特性の両方を理解した支援者につながることで、親子が孤立せず前向きに取り組むことができます。
まずは専門機関に相談してみませんか?
「家庭での工夫に限界を感じている」「ルールを決めても守れない」と悩んでいる方は、ぜひ専門機関や発達支援サービスにご相談ください。
私たちの放課後等デイサービス「煌光学園豊田キャンパス」でも、児童発達支援管理責任者が中心となり、保護者との面談や個別支援計画の作成を行っています。
教育現場と家庭の橋渡し役となり、先生方の負担を軽減するサポートも行っています。
お子さんの特性に合った方法を一緒に考えることで、親子にとって無理のない解決策が見つかります。安心できる環境づくりの第一歩を踏み出してみませんか。
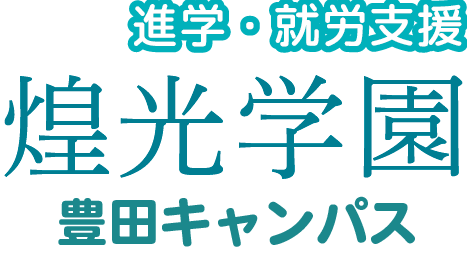
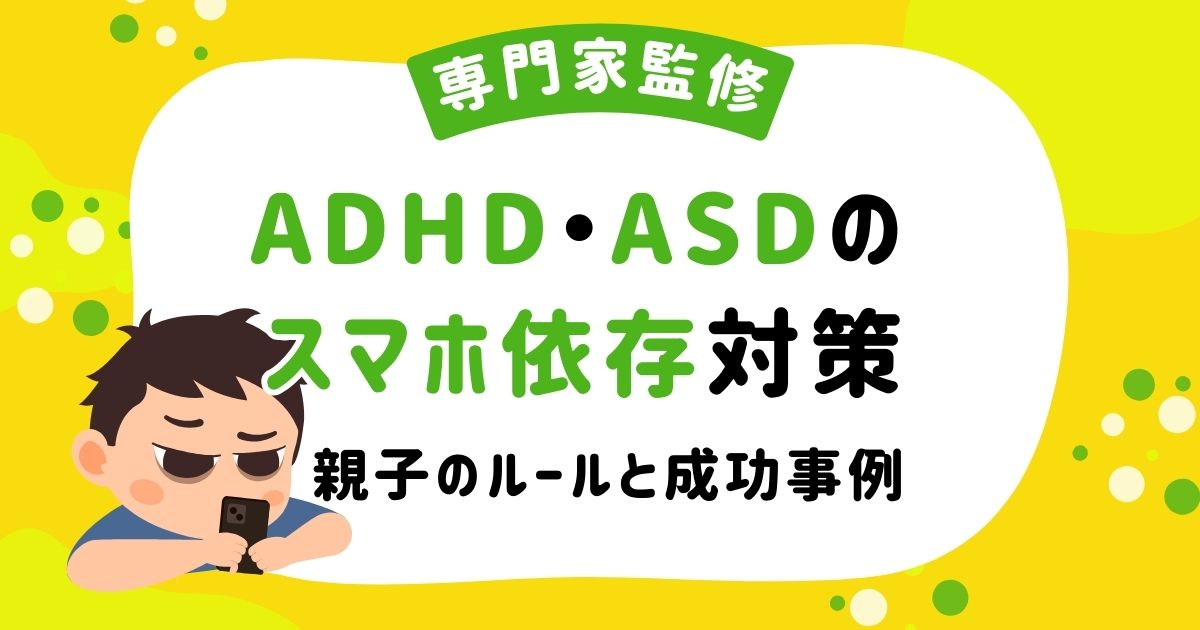
バナー-3.jpg)