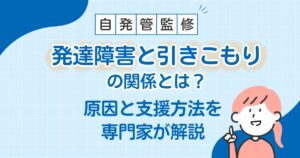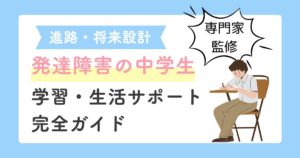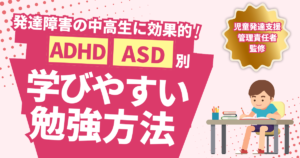「毎朝起こしてもなかなか起きられない」「遅刻や欠席が増えてしまう」と悩む保護者は少なくありません。
発達障害(ADHD・ASD・LDなど)のある子どもには、睡眠リズムの乱れや起立性調節障害などが関係しているケースもあります。
本記事では、現役の放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者として、原因の整理と対応方法、医療・学校との連携の仕方まで専門的に解説します。
発達障害と「朝起きられない」の関係

発達障害のある子どもが「朝なかなか起きられない」という悩みは、単なる生活習慣の乱れだけでなく、特性に深く関係していることがあります。
ADHDやASDの特性から睡眠リズムが崩れやすいことも多く、また起立性調節障害や睡眠障害を併発するケースも少なくありません。まずは背景を正しく理解することが、対応や支援の第一歩となります。
ADHDやASDの特性と睡眠リズムの乱れ
ADHDの子どもは、不注意や多動・衝動性だけでなく「入眠の難しさ」や「眠りが浅い」といった睡眠の困難を抱えることがよくあります。
脳内の覚醒システムが過敏に働くため、夜になっても気持ちが落ち着かず、寝つきに時間がかかるのです。
その結果、十分に眠れないまま朝を迎え、起きられなくなります。
一方、ASDの子どもは「生活リズムの変化への柔軟性の低さ」が関係し、就寝時間や起床時間がずれると整えにくくなります。
また感覚過敏によって「光がまぶしくて眠れない」「小さな物音が気になる」といった睡眠の妨げが起こる場合もあります。
このように、ADHDやASDそれぞれの特性が睡眠リズムに影響し、朝の起床困難につながります。
「怠けているから起きない」のではなく、発達特性が背景にある可能性を理解しておくことが重要です。
起立性調節障害(OD)や睡眠障害との違いと併存の可能性
発達障害の子どもが「朝起きられない」とき、しばしば関わってくるのが起立性調節障害(OD)です。
ODは自律神経の働きが不安定になることで、朝起きたときに強い倦怠感や頭痛、立ちくらみが起こり、布団から出られない状態が続く病気です。
午前中は体調が悪くても、午後になると元気になるのが特徴で、周囲から「さぼっている」と誤解されやすい点が大きな悩みとなります。
また、不眠症や概日リズム睡眠障害といった睡眠障害が背景にある場合もあります。
夜遅くまで寝つけない、睡眠の質が低くて熟睡感が得られないといった困難は、ADHDやASDと重なって生じることが多く、慢性的な寝不足が朝の起床困難につながります。
大切なのは、発達障害の特性による「生活リズムの乱れ」と、医学的に診断されるODや睡眠障害を切り分けることです。
実際には発達障害とODや睡眠障害が併存しているケースも少なくなく、専門的な医療機関での診断が必要になります。
保護者が「怠け」や「気合不足」と考えてしまうと、子どもが抱える本当の困難を見落とすことになりかねません。
症状が続く場合は、早めに小児科や心療内科などへ相談することが望ましいでしょう。
朝起きられるようにする生活習慣の工夫

発達障害のある子どもが「朝起きられない」背景には、睡眠リズムの乱れや特性による感覚の敏感さが関係していることが多くあります。
家庭でできる工夫を積み重ねることで、少しずつ起床のしやすさを改善することが可能です。まずは睡眠環境を整えることが第一歩となります。
睡眠環境の整え方(光・音・寝る前の刺激の調整)
子どもの睡眠の質を高めるためには、「寝室の環境づくり」がとても重要です。
ASDの子どもは感覚過敏をもつことが多く、わずかな光や音で眠れなくなることがあります。
遮光カーテンやアイマスクを活用し、外の光を遮ることで眠りに入りやすくなります。
また、時計の音や家族の生活音が気になる場合は、耳栓やホワイトノイズを使う方法も効果的です。
寝る前の過ごし方にも注意が必要です。
ゲームや動画など強い光刺激を与えるスクリーンタイムは、脳を覚醒させて入眠を妨げます。
就寝の1時間前からはブルーライトを避け、静かな読書やリラックスできる音楽を取り入れるとよいでしょう。
さらに、寝る時間と起きる時間をなるべく一定に保つことが大切です。
休日も大きく崩さないようにすると、体内時計が安定し、自然と朝に目が覚めやすくなります。
環境と生活リズムを整えることは、発達障害の子どもにとって「朝起きられる力」を育む基盤になるのです。
朝のルーティンづくりとアラームの工夫
朝の起床をスムーズにするためには、「毎日の決まった流れ=ルーティン」を作ることが効果的です。
例えば「起きたらカーテンを開ける → 顔を洗う → 朝食をとる」というように、一連の行動をパターン化しておくと、子どもは次に何をするかが予測でき、動きやすくなります。
ASDの子どもは特に見通しがあることで安心しやすいため、ルーティンを絵やチェックリストにして視覚的に提示するのも有効です。
また、アラームの工夫もポイントです。
大音量で一度に起こすよりも、複数回鳴るアラームや、音楽・振動・光を組み合わせたタイプのほうが効果がある場合があります。
ADHDの子どもは注意が散りやすいため、アラーム音を変える・スマートライトで徐々に明るくするなど、変化をつけると目が覚めやすくなることもあります。
重要なのは「子どもに合った方法を試しながら見つける」ことです。
家庭でできるサポートと親の声かけ
朝起きられない子どもに対して、保護者がどのように声をかけるかは大きな影響を与えます。
「早くしなさい」「なんで起きられないの」といった叱責はプレッシャーとなり、かえって布団から出られなくなることがあります。
代わりに、「一緒に顔を洗おう」「今日は〇〇があるよ」といった前向きな声かけを心がけましょう。
また、起床直後は体がだるく動きにくい場合も多いため、冷たいタオルを渡す、好きな音楽を流すなどの工夫で感覚を刺激するのも有効です。
家族の協力体制を整え、親一人が抱え込まずに支援できるようにすると、朝のストレスが軽減します。
「怠けているのではなく、特性や体の仕組みで難しい部分がある」という理解をもつことが、親子関係の悪化を防ぎ、子どもが安心して一日を始められる大きな支えになります。
学校との連携と配慮を求める方法

発達障害の特性や体調の影響で「朝起きられない」状態が続くと、どうしても遅刻や欠席が増えてしまいます。
家庭だけで解決しようとすると親子ともに負担が大きくなるため、学校と連携し理解を得ることが重要です。合理的配慮を求めることで、子どもが安心して学び続けられる環境を整えることができます。
遅刻・欠席が続くときの学校への相談の仕方
遅刻や欠席が目立つようになったときは、担任や学年主任に早めに相談することが大切です。
単に「朝起きられない」と伝えるだけでなく、背景にある発達障害の特性や、医師から診断を受けている場合はその内容を共有すると理解が得られやすくなります。
相談の際には、以下のような工夫が効果的です。
- 子どもの体調や生活リズムの記録を持参し、客観的に状況を示す
- 朝の起床困難が怠けではなく医学的・発達特性による可能性があることを説明する
- 家庭で取り組んでいる工夫(睡眠環境の調整、アラームの活用など)を具体的に伝える
また、学校側にお願いできる配慮としては「遅刻しても受け入れてほしい」「午前中は保健室登校から始めたい」「課題提出で評価に反映してほしい」といった具体的な方法を話し合うとよいでしょう。
教師にとっても対応の目安がわかりやすくなり、子どもが学びの機会を失わずにすみます。
合理的配慮としての柔軟な対応を依頼するポイント
発達障害のある子どもが「朝起きられない」ことで遅刻や欠席が続くと、成績や出席日数に直接影響してしまいます。
しかし、学校教育法や文部科学省の通知でも示されているように、特性や体調に応じた合理的配慮を学校に求めることが可能です。
依頼の際には「叱らずに受け入れてほしい」という感情的な訴えだけでなく、具体的な支援の形を提案することが大切です。たとえば、
- 午前中は保健室や別室から登校を始める
- 遅刻した場合でも授業に参加できる体制を整えてもらう
- 提出物や課題の期限を柔軟にしてもらう
- ICT教材や家庭学習の取り組みを評価に反映してもらう
などが挙げられます。
こうした配慮は、子どもの「学習権」を守るためのものです。
学校側にとっても、保護者から「医師の診断書」「家庭での記録」「支援の希望内容」を整理して伝えてもらえると、対応を検討しやすくなります。
「怠けているのではなく、体の仕組みや発達特性によるもの」という理解を広げ、子どもが安心して学校に通える環境を整えることが、結果的に進級や進路選択にもつながっていきます。
医療機関や専門機関でできること
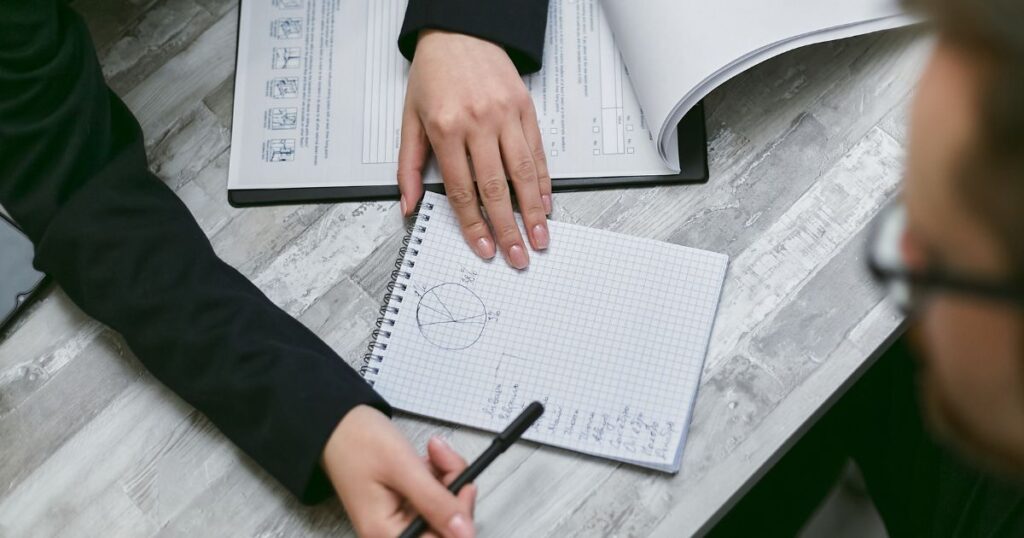
家庭での工夫や学校との調整をしても改善が難しい場合は、医療機関や専門機関に相談することが必要です。
「朝起きられない」状態の背景には、起立性調節障害や睡眠障害、あるいは発達特性による生活リズムの乱れが隠れている可能性があるため、専門的な視点で評価を受けることが安心につながります。
どこに相談すればいい?(小児科・心療内科・睡眠外来)
最初の相談先としては小児科が一般的です。成長や発達の状態を把握したうえで、必要に応じて専門医を紹介してもらえます。思春期の子どもであれば、小児心療内科や児童精神科が対応してくれるケースも多く、発達障害との関連や心理的ストレスを含めて総合的に評価してもらえます。
また、「寝つけない」「昼夜逆転している」「熟睡できない」など睡眠そのものの困難が強い場合は、睡眠外来や専門クリニックでの診察が有効です。
近年では子どもの睡眠障害に特化した医療機関も増えており、客観的な検査をもとに適切な治療方針を立ててもらえます。
薬物療法・認知行動療法・生活リズム支援の選択肢
医療機関では、症状に応じていくつかの支援方法が選択されます。
代表的なのは薬物療法で、起立性調節障害には自律神経を整える薬が処方されることがあり、ADHDの子どもには睡眠をサポートする薬が使われる場合もあります。
ただし、薬はあくまで補助的な手段であり、医師の指導のもとで慎重に行う必要があります。
薬以外の方法としては、認知行動療法(CBT)によって睡眠への考え方や行動パターンを整える支援があります。
また、専門スタッフと一緒に生活リズムを組み立て、起床時間や就寝前の行動を改善していく生活リズム支援も効果的です。
家庭や学校の取り組みだけでは限界があるケースも多いため、医療機関や専門機関と連携しながら多角的にアプローチすることが、子どもが「朝を迎えやすくする」大きな助けになります。
学校生活と進路への影響

「朝起きられない」ことが続くと、学校生活への影響は少なくありません。
単なる生活リズムの乱れと捉えられてしまうと、子どもや家庭に大きな負担がのしかかります。
将来の進級や進路選択にも直結するため、早めに影響を理解し、制度的な支援を活用することが重要です。
遅刻や欠席が成績・進級・受験に与える影響
遅刻や欠席が増えると、まず影響を受けるのは成績評価や内申点です。
授業に出られないことで理解不足が生じ、課題提出の遅れも重なると、本人の学力や努力に関係なく低く評価される場合があります。
また、内申点は進学に直結するため、「起きられない」という特性が高校受験や大学進学に不利に働くケースも少なくありません。
ただし、学校によっては事情を理解し、授業の振り返りや課題提出で評価を補う対応をしてくれるところもあります。
保護者が早めに状況を共有し、学校と一緒に解決方法を探ることで、子どもが将来のチャンスを失わずにすむ可能性が広がります。
教育委員会や特別支援教育制度の活用
学校だけで支援が難しい場合は、教育委員会や特別支援教育の制度を活用する方法もあります。
たとえば「通級による指導」や「特別支援学級」では、個別に配慮した学習支援が受けられることがあります。
また、医師の診断や支援計画に基づいて「出席扱い制度」を適用できれば、在宅や外部の学習支援サービスで学んだ内容を学校の出席として認めてもらえる可能性もあります。
さらに、放課後等デイサービスや教育委員会の相談窓口を通じて、家庭・学校・医療をつなぐ支援会議を開くことも可能です。
子どもにとって最適な学びの環境を確保するには、保護者が「制度を知り、必要な支援を組み合わせる」姿勢が欠かせません。制度の活用は、子どもが進路の選択肢を広げる大切なカギになります。
親の気持ちと家庭のストレスへの向き合い方

「朝起きられない」ことが続くと、学校生活への影響は少なくありません。
単なる生活リズムの乱れと捉えられてしまうと、子どもや家庭に大きな負担がのしかかります。
将来の進級や進路選択にも直結するため、早めに影響を理解し、制度的な支援を活用することが重要です。
「怠け」ではなく特性と理解するために
遅刻や欠席が増えると、まず影響を受けるのは成績評価や内申点です。
授業に出られないことで理解不足が生じ、課題提出の遅れも重なると、本人の学力や努力に関係なく低く評価される場合があります。
また、内申点は進学に直結するため、「起きられない」という特性が高校受験や大学進学に不利に働くケースも少なくありません。
ただし、学校によっては事情を理解し、授業の振り返りや課題提出で評価を補う対応をしてくれるところもあります。
保護者が早めに状況を共有し、学校と一緒に解決方法を探ることで、子どもが将来のチャンスを失わずにすむ可能性が広がります。
叱る?支える?迷うときの考え方
学校だけで支援が難しい場合は、教育委員会や特別支援教育の制度を活用する方法もあります。
たとえば「通級による指導」や「特別支援学級」では、個別に配慮した学習支援が受けられることがあります。
また、医師の診断や支援計画に基づいて「出席扱い制度」を適用できれば、在宅や外部の学習支援サービスで学んだ内容を学校の出席として認めてもらえる可能性もあります。
さらに、放課後等デイサービスや教育委員会の相談窓口を通じて、家庭・学校・医療をつなぐ支援会議を開くことも可能です。
子どもにとって最適な学びの環境を確保するには、保護者が「制度を知り、必要な支援を組み合わせる」姿勢が欠かせません。制度の活用は、子どもが進路の選択肢を広げる大切なカギになります。
兄弟姉妹や家族全体の生活リズムへの影響
子どもが朝なかなか起きられない状態が続くと、家庭全体の生活リズムにも影響が及びます。
保護者は毎朝、何度も声をかけたり学校への連絡をしたりする必要があり、その負担が積み重なって疲弊してしまいます。
また、兄弟姉妹がいる場合、「どうして自分だけがきちんと登校しなければならないのか」と不満を持ったり、逆に「お兄ちゃん(お姉ちゃん)は怠けているのでは」と誤解を抱くこともあります。
このような家庭内の不均衡は、兄弟姉妹の自己肯定感や親子関係に影響を与える可能性があります。
さらに、家族全員の朝の時間が慌ただしくなり、親の仕事への出発や他の子どもの準備まで遅れてしまうと、家族全体がストレスを抱える状況になりかねません。
大切なのは、家庭の中で「本人の特性による困難である」という理解を共有することです。兄弟姉妹にも年齢に応じて説明し、協力できる部分をお願いすることで不公平感を和らげられます。
また、親が一人で抱え込まずに、配偶者や祖父母、時には支援サービスの力を借りることも有効です。家庭全体の負担を軽減しながら、安心できる朝のスタートを整えることが、長期的な支援には欠かせません。
改善事例と希望を持つために

「朝起きられない」困難は長く続くと親子ともに疲弊し、「このまま学校に通えないのでは」と将来への不安を抱きやすくなります。
しかし、生活習慣の工夫や専門的な支援を受けることで改善が見られた事例も多くあります。実際の取り組みを知ることで、「自分の子どもにもできることがある」と希望を持てるでしょう。
生活習慣や支援で改善した事例
ある中学生の事例では、ADHDによる夜更かしが習慣化していました。
そこで家庭では「寝る前のスクリーンタイムを30分短縮」「朝はカーテンを自動で開けるライトアラームを導入」したところ、1か月ほどで徐々に登校できる日が増えていきました。
また、起立性調節障害と診断された高校生は、午前中の登校が難しく欠席が続いていましたが、学校と相談し「午前中は保健室登校、午後から授業参加」という柔軟な形を取ったことで、進級に必要な単位を確保できました。
その後、生活リズム支援を受けながら、登校時間を少しずつ早められるようになったケースもあります。
さらに、放課後等デイサービスを活用して「生活リズムの記録」「自己管理のスキル練習」を継続した子どもでは、半年後に遅刻が減り、自信を取り戻したという報告もあります。
このように、小さな工夫と支援の積み重ねで改善は十分に可能です。「一朝一夕ではなく、少しずつ取り組む」ことが成功のカギとなります。
進学や就職につなげられる可能性
「朝起きられない」という課題があると、保護者は「将来、進学や就職に支障が出るのでは」と不安を抱きやすいものです。
確かに遅刻や欠席が多いと、内申点や学習の進度に影響を及ぼします。
しかし、支援を受けながら改善に取り組むことで、進学や社会参加の道をしっかり切り開いている子どもたちも数多くいます。
例えば、高校進学を控えたある生徒は、出席扱い制度を活用して放課後等デイサービスでの学習を学校の評価に反映してもらいました。
その結果、登校日数が不足していても進学に必要な単位を確保することができました。
また、大学進学の段階では「オンライン授業の活用」や「合理的配慮による柔軟な出席認定」を受けることで学びを継続できた事例もあります。
就職においても、近年は障害者雇用の場が広がり、柔軟な勤務形態を取り入れる企業も増えています。
朝の始業時間に合わせることが難しい場合でも、午後から働ける職場や在宅勤務の選択肢が用意されているケースがあります。
重要なのは、「朝起きられない=将来が閉ざされる」ではないということです。
子どもの特性に合わせた環境を整え、進学や就職につながるサポートを受け続けることで、自分らしい未来を実現できる可能性は十分にあります。
まとめ│朝起きられない子どもへの理解と支援が未来を拓く
発達障害のある子どもが「朝起きられない」とき、その背景には睡眠リズムの乱れや起立性調節障害、感覚過敏など、さまざまな要因が関係しています。単なる怠けや親の関わり方だけで説明できるものではありません。
家庭での生活習慣の工夫や学校への相談、医療機関での専門的な支援を組み合わせることで、少しずつ改善していくことは十分可能です。
大切なのは「できないことを叱る」のではなく、「特性に応じてどうサポートできるか」を考える姿勢です。
子ども自身が「起きられない自分」を責めず、安心して一日を始められるようになることが、学習や進路、将来の自立へとつながっていきます。
まずは専門機関に相談してみませんか?
「朝起きられない」困難が続くと、家庭だけで解決しようとしても限界があります。
そんなときは、児童発達支援や放課後等デイサービス、小児科や心療内科などの専門機関に相談することが第一歩です。
当施設でも、発達障害の特性に合わせた生活リズムの支援や学習支援を行っています。お子さまの「できない」を「できる」に変えていくために、ぜひ一度ご相談ください。
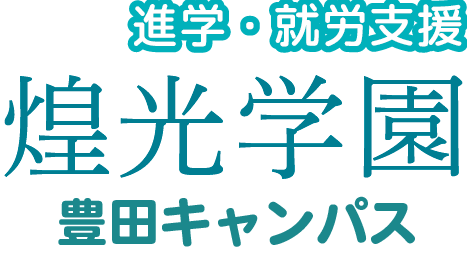
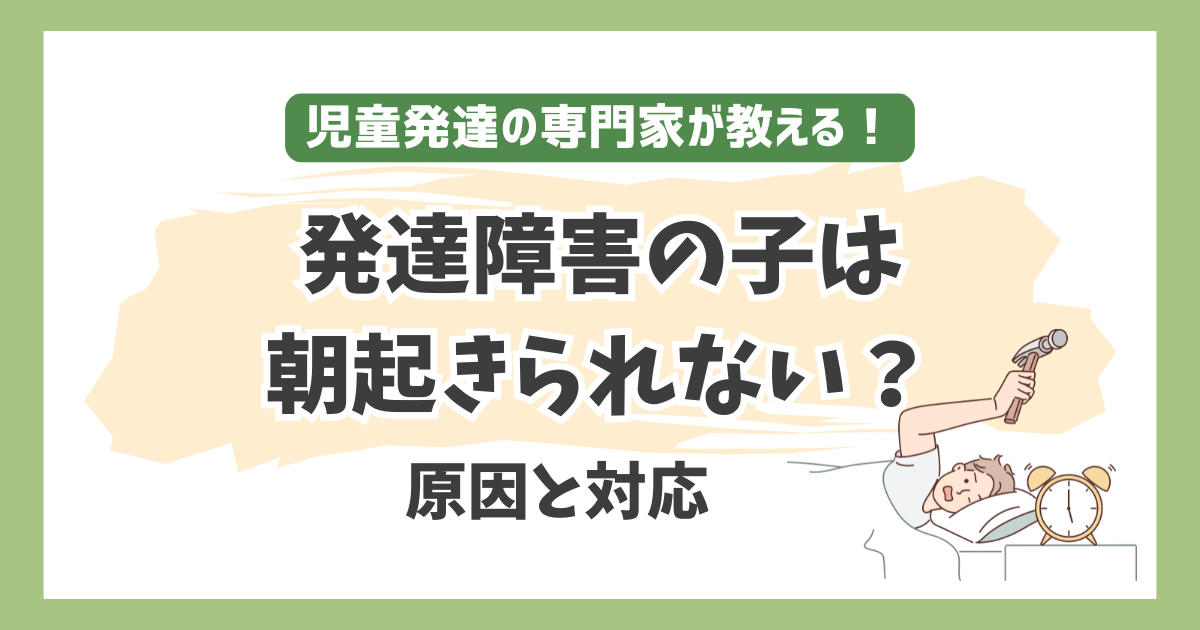
バナー-3.jpg)