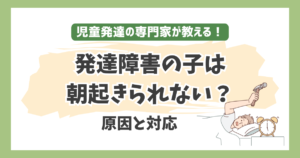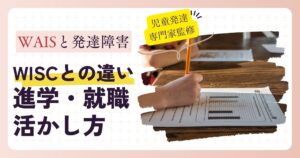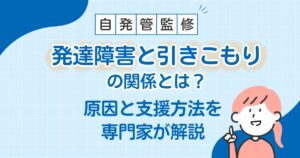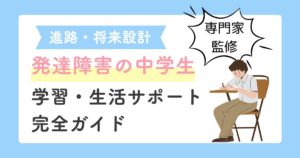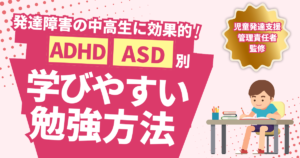「うちの子は勉強ができないのでは…」と悩む保護者は少なくありません。
特に発達障害(ASD・ADHD・LD)のある子どもは、集中が続かない、文字を読むのに時間がかかる、計算が苦手といった特性から、学習面でつまずきやすいことがあります。
しかし、「勉強できない」というのは単なる能力不足ではなく、その子の特性に合った学び方に出会えていないだけの場合も多いのです。
本記事では、発達障害の子どもが勉強でつまずく背景や原因を整理し、家庭や学校・塾でできる具体的なサポート方法をご紹介します。
さらに、将来の進路選択や相談先についても解説します。保護者や先生が子どもの特性を理解し、適切な支援につなげることで、学びへの自信と可能性を広げていきましょう。
発達障害の子どもが「勉強できない」と見える理由
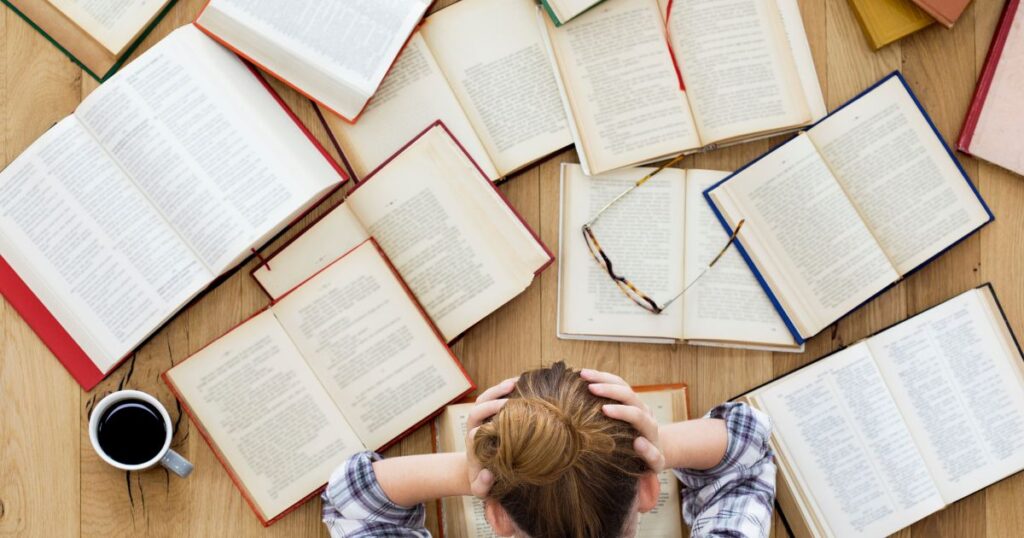
発達障害のある子どもが「勉強できない」と感じられる背景には、知能や努力不足ではなく特性に基づく学習のつまずきがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)といった診断名によって現れ方は異なりますが、いずれも「理解の仕方」や「集中の仕方」が定型発達の子どもと違うために、結果として成績や授業態度に影響することが多いのです。
ここではそれぞれの特性と、学習面での課題を整理していきます。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性と学習のつまずき
ASDの子どもは、得意・不得意の差が大きいことが特徴です。
興味関心のある分野では驚くほどの集中力を発揮する一方で、抽象的な概念や複数の情報をまとめて理解することが苦手な場合があります。
例えば、国語の読解では登場人物の気持ちを推測する問題につまずきやすく、算数では文章題の意図を読み取れず計算まで進めないことがあります。
また、こだわりが強いため「やり方を変えるのが難しい」「一度間違うとパニックになる」といった行動が見られることもあります。
こうした特性は「勉強ができない」という印象を持たれやすいですが、視覚支援や手順の明示などの工夫を加えることで理解度が大きく変わることがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)の特性と学習のつまずき
ADHDの子どもは、不注意・多動性・衝動性といった症状により学習環境で困難を抱えやすいです。
不注意の傾向が強い場合は、黒板の内容をノートに書き写す途中で気が散り、最後まで記録できないことがあります。
多動性が強い場合は、授業中にじっと座っていること自体が大きな負担となり、内容が頭に入らなくなることもあります。
また、衝動性があると「考える前に答えてしまう」「順番を守れない」といった行動につながり、学級内で叱られる機会が増え、自己肯定感の低下を招きやすいのも特徴です。
これらは本人の努力不足ではなく、脳の働きの特性によるものです。学習を短時間に区切る、視覚的にやることを明示するなどの配慮が有効です。
LD(学習障害)の特性と学習のつまずき
LD(学習障害)は、知的発達に遅れはないものの「読む・書く・計算する」といった特定の学習分野に著しい困難がある状態です。
たとえば、ディスレクシア(読みの困難)がある子は文字を一字一字追うのに時間がかかり、教科書を読むこと自体が大きな負担になります。ディスグラフィア(書字の困難)では漢字を正しく書けない、板書が極端に遅いといった困難が目立ちます。
また、ディスカリキュリア(算数障害)の場合は数の概念や計算手順を理解するのに時間がかかり、繰り返しても定着しにくいことがあります。
こうした課題は「勉強ができない」と誤解されがちですが、ICT教材や補助具の利用で克服できるケースも多くあります。
共通する項目(集中できない・読むのが遅い・計算が苦手・指示が理解できない)
ASD・ADHD・LDの子どもたちに共通するのは、「理解はできてもアウトプットに時間がかかる」「集中力にムラがある」という点です。
授業のペースに合わせられず「できない子」と思われたり、課題が終わらないことで自己肯定感が下がるケースも少なくありません。
例えば、読むのが遅い子は教科書の音読で置いていかれ、計算が苦手な子は算数のテストで時間切れになりがちです。
また、先生の指示を一度で理解できず、行動が遅れることで叱責されることもあります。
こうした困難さは「特性の表れ」であり、本人の努力不足ではありません。支援や工夫によって改善できる余地が大いにあります。
学習が苦手な子への効果的な勉強方法

発達障害のある子どもが「勉強できない」と感じられる背景には、その子に合った方法に出会えていないという側面があります。
標準的な授業スタイルが合わなくても、環境や教材、支援の仕方を工夫することで学びやすさは大きく変わります。ここでは効果的な勉強方法の具体例をご紹介します。
また、発達障害の中高生に効果的な勉強方法について下記の記事で詳しく解説していますので、こちらも併せて参考にしてくださいね。

タブレット教材やICTを活用する
近年はタブレットやPCを用いたICT教材が普及し、発達障害のある子どもの学習に大きな助けとなっています。
例えば、読みが苦手な子には文字を音声で読み上げてくれる機能が有効ですし、計算が苦手な子には視覚的に数を操作できるアプリが役立ちます。
また、紙の教材よりもカラフルでインタラクティブな画面は、ADHDの子どもの興味を引きやすく、「やってみたい」という気持ちにつながります。
学校や塾での補助だけでなく、自宅学習の継続にも効果的です。
スモールステップで達成感を積み重ねる
「一度に多くの内容を学ばせる」のではなく、「小さな単位に分けて段階的に進める」ことが重要です。
例えば、漢字を一度に10個覚えるのではなく、まずは2~3個から始めて成功体験を積み重ねる、といった形です。
スモールステップの工夫によって「できた!」という感覚を持てると、学習に対する自信が芽生え、次の課題にも前向きに取り組めるようになります。
失敗体験の積み重ねが自己肯定感を下げやすい発達障害の子どもにとって、この「達成感の積み重ね」は特に有効です。
視覚支援・チェックリストの工夫
ASDやADHDの子どもは、口頭での説明だけでは理解が難しい場合があります。
そのため、手順ややることを「目で見てわかる形」にする視覚支援が効果的です。
例えば、宿題の順番をイラスト付きのチェックリストにまとめる、テスト前に「やることカード」を作る、といった方法があります。
また、時計やタイマーを活用して「あと5分で終わり」など時間を見通せるようにすると、集中が途切れにくくなります。
こうした視覚支援は学校や塾だけでなく、家庭学習にも取り入れやすい工夫です。
個別指導や家庭教師を活用する
集団授業の中ではつまずきが目立ってしまう子でも、マンツーマンや少人数であれば落ち着いて学べることがあります。
特に家庭教師や発達障害対応の個別指導塾では、特性に合わせた進め方が可能です。
例えば、「文字を読むのが苦手だから代わりに読み上げをし、内容理解に集中する」「座っていられるのは10分なので、その後は実技やプリントに切り替える」といった柔軟な対応ができます。
こうした個別最適化された学習は「できない子」ではなく「こうすればできる子」として成長を支える基盤になります。
煌光学園豊田キャンパスと同グループが運営しているぽかぽかステップランド スタディホップは、発達支援児専門の個別指導塾です。
筆者と同じ発達支援の専門家である「児童発達支援管理責任者」が常駐し、一人ひとりの性格や特性に合わせた学習・生活サポートをしております。
無料体験受付中ですので、ぜひお問い合わせください!
ご家庭でできるサポート方法

学校や塾での支援も大切ですが、最も長い時間を過ごす家庭での関わり方が学習意欲に直結します。
保護者の声かけや環境調整の工夫次第で、「勉強が嫌い」から「少しずつ取り組める」へと変化する子どもも少なくありません。ここでは家庭でできる実践的なサポート方法を紹介します。
声かけやモチベーションの工夫
「早く勉強しなさい」ではなく、「一緒にやってみよう」「ここまでできたら休憩しよう」といった前向きな声かけが効果的です。
発達障害のある子どもは「できないこと」に直面する機会が多く、叱責されることで自己肯定感が下がりやすい傾向があります。
そのため、「できた部分をほめる」「頑張った過程を認める」ことが大切です。
例えば、宿題が終わらなくても「机に向かえたね」「1問は解けたね」と評価することで、子どもは次のチャレンジに前向きになります。
勉強環境の整え方(音・光・座席など)
学習のしやすさには環境要因も大きく影響します。
ADHDの子は周囲の音や視覚刺激で注意が散りやすいため、机の上をシンプルに整えたり、視界に入る壁に余計な掲示物を貼らないといった工夫が効果的です。
また、ASDの子は蛍光灯のちらつきや音に敏感な場合があるため、スタンドライトを使う、静かな個室を用意するなど環境調整が役立ちます。
座る位置も「窓際やテレビの近く」より「静かで落ち着ける隅の席」の方が集中できる場合が多いです。
親子関係を悪化させない接し方
「勉強しなさい」と繰り返すことで親子関係が悪化するケースは少なくありません。
保護者の焦りは理解できますが、毎日のように叱責が続けば子どもは勉強自体を嫌悪するようになります。
大切なのは「勉強=親子バトル」にならないことです。
時間を区切り、学習が終わったら好きなことを一緒に楽しむなど、ポジティブな時間も確保しましょう。
また、保護者が子どもの努力を認める姿勢を持つことで、勉強に対するネガティブな印象を減らせます。
学校・塾で受けられる支援と合理的配慮

発達障害のある子どもが学習に前向きに取り組むためには、家庭だけでなく学校や塾での支援も欠かせません。
日本では「合理的配慮」という考え方が広がり、子どもの特性に応じて学びやすい工夫を行うことが求められています。ここでは、学校や塾で期待できる支援内容を整理します。
学校での支援体制(通級・合理的配慮・特別支援学級)
学校では、通常学級に在籍しながら必要な時間だけ支援を受けられる「通級指導教室」や、より手厚いサポートを受けられる「特別支援学級」が設けられています。
また、通常学級でも合理的配慮が取り入れられるケースがあります。たとえば、
- テスト時間の延長
- 問題文の読み上げ
- 席を前列や壁際にする
- プリントを大きな文字にする
といった配慮です。
これらは「甘やかし」ではなく、その子の力を正しく発揮するための工夫であり、学習到達度を公平に評価するために必要なものです。
塾や放課後等デイサービスでの学習支援
近年は、発達障害のある子に対応した個別指導塾や学習支援特化型の放課後等デイサービスも増えています。
塾では学校の授業フォローや受験対策に特化し、放課後等デイサービスでは「学習+生活スキル」や「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」を組み合わせて支援することが一般的です。
特に発達障害対応の塾では、少人数制やマンツーマンを取り入れることで「子どもの特性に合った学び方」を見つけやすく、自己肯定感の回復にもつながります。
私たち煌光学園も、発達特性のある中高生の進学・就職をサポートしている放課後等デイサービスのひとつです。
一人ひとりの性格や発達特性に合わせた個別支援計画のもと、学習だけでなく生活や進路の支援をしております。
詳しくは公式HPをご覧のうえ、無料体験にお申し込みください。
進路指導や受験時の配慮
高校受験や進学の際には、学校や塾で進路相談が行われます。
発達障害のある子どもの場合、以下のような配慮が検討されることがあります。
- 内申点よりも当日の試験を重視する学校の選択
- 出題形式や受験会場での環境調整(例:別室受験)
- 面接時の質問形式の工夫
また、合理的配慮を求めるには「医師の診断書」「学校からの意見書」が必要な場合があるため、早めに担任や進路指導の先生と相談しておくことが大切です。
勉強が苦手でも広がる進路の選択肢

「勉強ができないと将来が閉ざされてしまうのでは…」と不安に思う保護者は少なくありません。
しかし、発達障害のある子どもたちには、学力偏差値だけでなく特性や得意分野を活かした進路が数多く存在します。
大切なのは「できないこと」ではなく「できること」に目を向け、本人に合った進路を一緒に探していくことです。
高校受験に向けたサポート
発達障害のある子どもでも、適切な支援と準備があれば高校進学は十分に可能です。
最近では、出題形式を工夫したり、推薦枠を活用できる学校も増えています。
学力試験だけでなく、面接や作文で評価する学校もあるため、本人の強みを発揮しやすい受験方法を選ぶことが大切です。
また、塾や学校での進路指導を受けながら「受験時の合理的配慮(別室受験や時間延長など)」について事前に相談しておくと安心です。
専門学校・職業訓練校という選択
「学力テストが苦手」でも、専門学校や職業訓練校では、実技や実習を中心に学ぶことで得意を伸ばせる環境があります。
例えば、調理・介護・デザイン・ITなど、実践力を重視する分野は、座学が苦手な子でも力を発揮しやすい場です。
発達障害の子にとっては「手を動かしながら学べる」スタイルが合うことが多く、専門性を身につけることで将来の就労にもつながります。
特別支援学校や福祉的就労の可能性
学習面での困難が大きい場合は、特別支援学校への進学や、卒業後に就労支援事業所を利用する選択肢もあります。
支援学校では学習と並行して、生活スキルや職業訓練に重点を置くカリキュラムが組まれており、「自立に向けた力」を養いやすいのが特徴です。
さらに、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)といった制度を活用すれば、障害特性に配慮された環境で働く準備を進めることも可能です。
煌光学園では、同フロア内に同グループが運営している就労継続支援事業所A・B型キラキラがあります。就労支援事業所で働く人々を見ながら、職場体験をしたり就労スキルを身につけられる環境です。
得意分野を伸ばして社会につなげる方法
発達障害のある子は、「勉強」ではつまずいても、芸術・音楽・プログラミング・スポーツなどに強みを持つケースが多くあります。
大切なのは、その才能を早く見つけて伸ばすことです。
例えば、プログラミングに強い関心があれば専門的なスクールや部活動につなげる、絵や音楽に秀でていればコンクールに挑戦するなど、学外での経験が自己肯定感を高めます。
その経験は将来の進学・就職の際に「強み」として評価されることも少なくありません。
相談先と支援機関の活用

「勉強ができない」という悩みを家庭だけで抱え込むのは、親子双方にとって大きな負担になります。
発達障害の特性や学習上の困難については、地域の相談窓口や専門機関につなぐことで、より適切な支援が受けられます。ここでは代表的な相談先を紹介します。
発達支援センターや相談窓口
市区町村には「発達支援センター」「教育相談室」など、子どもの発達や学習に関する悩みを相談できる窓口があります。心理士や発達支援の専門スタッフが在籍しており、発達検査や就学に向けたアドバイスを受けることが可能です。
学校と連携して支援方針を立ててくれる場合もあり、「授業についていけない」「配慮をお願いしたい」といった悩みを整理する最初のステップとして活用できます。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までの発達障害のある子どもを対象に、学習支援や生活スキルのトレーニングを行う福祉サービスです。
宿題のフォローや個別学習のほか、SST(ソーシャルスキルトレーニング)を通じてコミュニケーション力を育てるプログラムも用意されています。
学校や家庭では難しい「第三の場」として、子どもが安心して学び、自分のペースで成長できる環境を提供してくれるのが特徴です。
発達障害対応の学習塾・家庭教師
学習面に特化してサポートを希望する場合は、発達障害に理解のある個別指導塾や家庭教師も有効です。こうした塾では、
- 学習内容を小さなステップに分ける
- ICT教材を積極的に導入する
- 宿題管理やスケジュール作成を一緒に行う
といった工夫が取り入れられています。
専門性の高い講師が担当することで「わかる」「できる」を積み重ねやすくなり、自己肯定感の回復にもつながります。
医療・カウンセリングの併用
学習の困難さが二次的に「不安」「うつ」「不登校」などを引き起こす場合もあります。
その際には、児童精神科や小児科など医療機関での受診を検討しましょう。必要に応じて薬物療法が併用されることもあります。
また、心理士によるカウンセリングは、子ども自身の気持ちを整理する助けになり、親へのペアレントトレーニング(関わり方の指導)としても有効です。
医療と福祉・教育を組み合わせることで、より包括的な支援が実現します。
まとめ│勉強できない子の「できる」を見つけよう
発達障害のある子どもが「勉強できない」と感じられる背景には、努力不足ではなく特性に合わない学び方が影響していることが多くあります。
ASD・ADHD・LDそれぞれに特有のつまずきはありますが、スモールステップの学習やICT教材、個別指導などの工夫を取り入れることで「できること」を増やしていくことが可能です。
また、家庭での前向きな声かけや環境調整、学校や塾での合理的配慮、福祉サービスや相談機関の活用など、周囲の支援が整えば子どもは自信を取り戻して学びに向かいやすくなります。
勉強の成果は将来の進路や就労に直結するだけでなく、自己肯定感や社会で生きる力にもつながります。
大切なのは「できない部分」ではなく「得意をどう伸ばすか」という視点です。
保護者や先生が伴走者となり、子どもの可能性を広げていきましょう。
「勉強できない」と悩む前に、お子さまに合った学び方を一緒に探してみませんか?
煌光学園豊田キャンパスでは、児童発達支援管理責任者が中心となり、一人ひとりの特性に合わせた学習支援・進路相談を行っています。
無料体験やご相談も随時受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください!
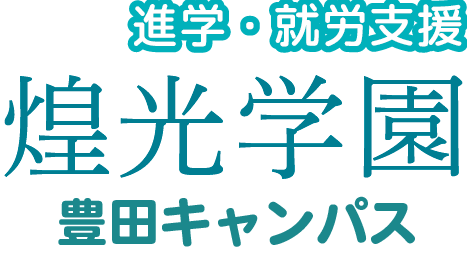
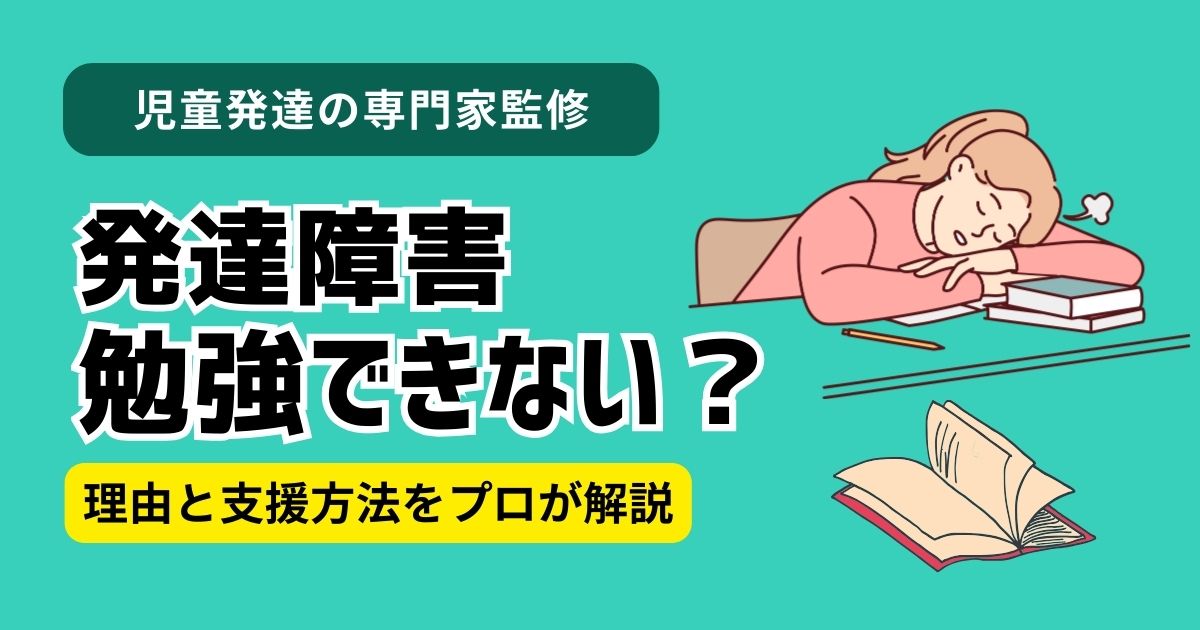
バナー-1.jpg)
バナー-2.jpg)
バナー-3.jpg)