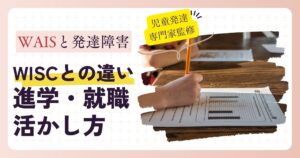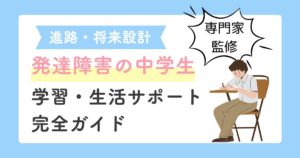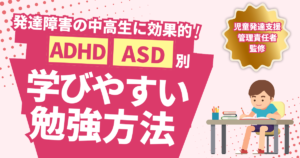発達障害がある人の就職活動の特徴

発達障害(ADHD・ASD・LDなど)のある方は、就職活動で一般の求職者とは異なる壁に直面することがあります。
たとえば、情報整理やスケジュール管理の難しさ、面接で自分の強みや適性をうまく言語化できない、職場環境への適応の時間がかかるといった点です。これらは本人の努力不足ではなく、脳の特性や情報処理の仕方の違いによるものです。
一方で、発達障害のある人には集中力の持続(ASDの特性)や新しい発想や行動力(ADHDの特性)など、職種によっては大きな武器になる強みもあります。自分の得意分野を理解し、それを活かせる職場を見つけることが、就職活動の成功の第一歩です。
特に、進学先や学校生活から就職活動に移行するタイミングでは、支援級や特別支援学校出身の場合、学校内の進路指導や実習先の紹介が重要な役割を果たします。一般就労を目指す場合も、早い段階から職業体験やアルバイトを通して「自分がどんな環境で働きやすいのか」を確認することが必要です。
また、就職活動は本人だけでなく、保護者や支援者がチームとして動くことで成功率が高まります。履歴書や面接対策だけでなく、応募先とのやりとりや就職後のフォローまで、一貫した支援体制を整えておくことが安心につながります。
就職活動の基本的な流れ就職活動の基本的な流れ
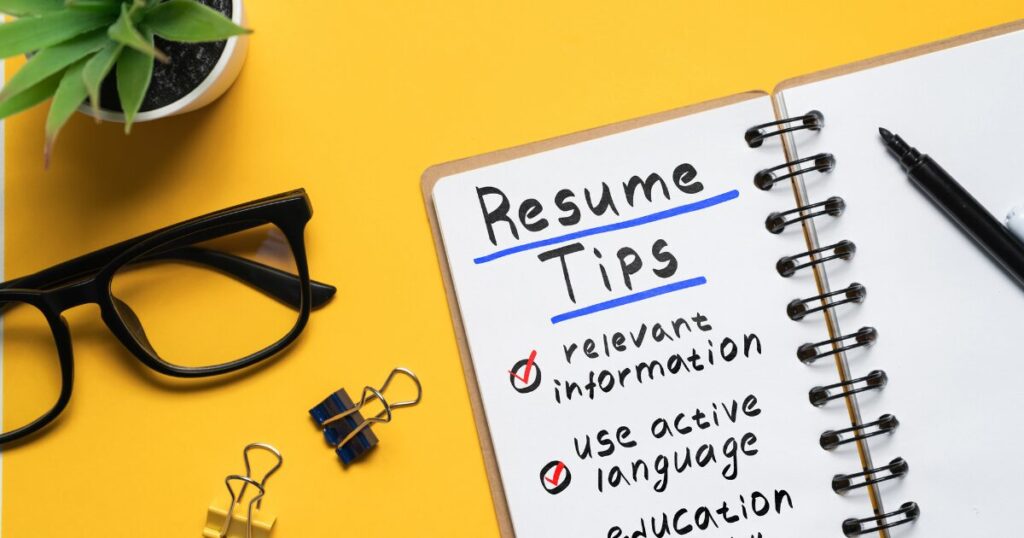
発達障害がある方の就職活動は、一般的な流れを押さえつつ、特性や環境への配慮を前提に計画的に進めることが大切です。
以下の4つのステップで整理すると、進めやすくなります。
まずは、自分の得意・不得意、興味関心、苦手な環境や状況を整理します。
これにより、自分に合う仕事や職場の条件が明確になります。
・支援者や家族と一緒に話し合い、特性を言語化する
・過去の学校生活やアルバイト経験から得た「働きやすかった状況・苦しかった状況」を振り返る
・必要に応じて心理検査やWAIS検査などで客観的データを活用する
WAIS検査は成人版(16歳以上)の認知機能検査で、WISC検査と同じようなものです。
WAISに関しては下記の記事で概要や活用法を詳しく解説していますので、ぜひ併せてお読みください。
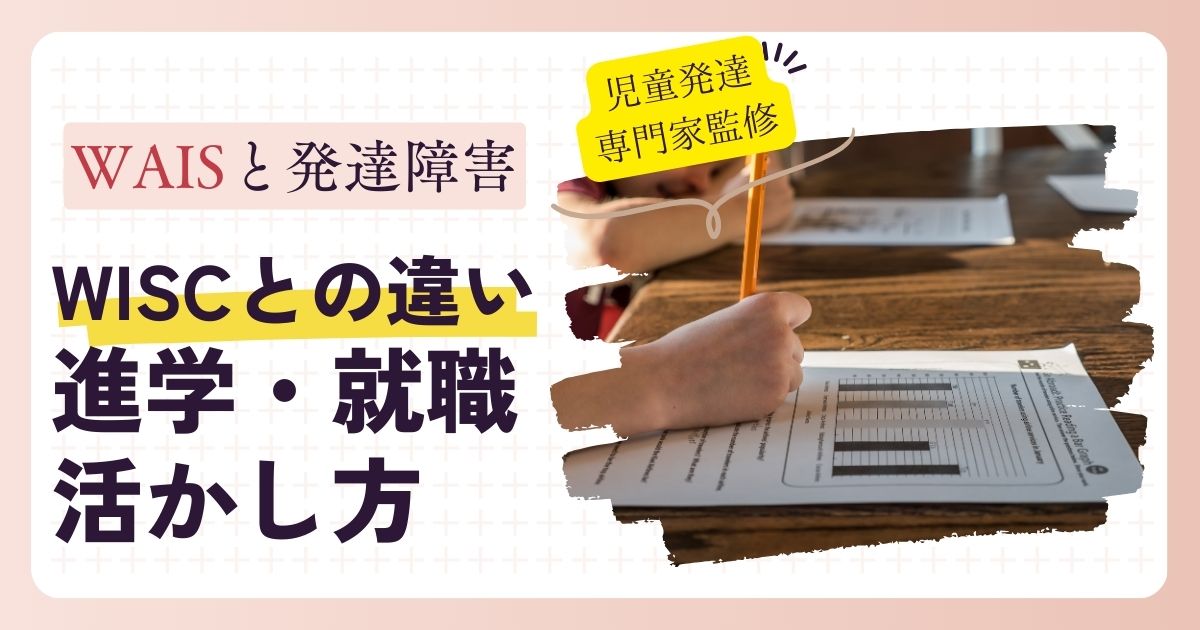
職業適性検査(ハローワークや職業センターで実施)や職場体験を通して、実際の仕事内容や環境が自分に合っているかを確認します。
・ASD傾向がある場合:作業の手順が明確で一人で集中できる仕事
・ADHD傾向がある場合:変化や動きのある仕事、短時間集中型の業務
就職先を探す際は、一般求人と障害者雇用枠の違いを理解しておきましょう。
- 一般求人:幅広い職種・条件があるが、配慮事項は事前に交渉が必要
- 障害者雇用枠:合理的配慮や特性に合わせた働き方の提案が受けやすい
学校の進路指導室、ハローワーク、就労移行支援事業所などを併用して探すのがおすすめです。
履歴書・職務経歴書は、特性を補う工夫や強みを活かした実績を具体的に書くことがポイントです。
面接では、配慮してほしいことを簡潔に説明し、代替策や自分なりの工夫も合わせて伝えると印象が良くなります。
例:「電話対応は苦手ですが、メールでのやり取りや書類作成は正確に対応できます」
発達障害のある人が利用できる就職支援制度

就職活動を単独で進めるのは、情報収集や対策面で負担が大きくなりがちです。
発達障害がある場合は、公的・民間の支援制度を活用することで成功率が大幅に高まります。ここでは主な支援先と内容を紹介します。
就労移行支援
障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、一般就労を目指す方を対象に最長2年間の就職準備プログラムを受けられます。
- ビジネスマナーやパソコンスキルの習得
- 模擬面接や履歴書作成のサポート
- 企業での実習体験
- 就職後6か月の職場定着支援
利用には市区町村の障害福祉課での申請が必要です。支援員が本人の特性を理解したうえで、企業との橋渡しをしてくれるのが大きなメリットです。
ハローワーク・専門窓口
全国のハローワークには「発達障害者雇用トータルサポーター」を配置している拠点があります。
- 特性に配慮した求人紹介
- 職場実習や体験のあっせん
- 面接同行や企業への配慮事項の説明
一般求人だけでなく、障害者雇用枠の求人にもアクセスできるため、選択肢が広がります。
障害者職業センター
厚生労働省所管の専門機関で、職業評価(得意・不得意の測定)や職場適応のための助言を受けられます。
必要に応じて職場実習をコーディネートしてくれ、雇用主への特性理解の説明も行ってくれます。
学校との連携
特別支援学校や支援級に在籍している場合は、進路指導担当やキャリア支援コーディネーターが就職活動をサポートしてくれることがあります。
- 職場見学やインターンシップの調整
- 企業との連絡・日程調整
- 卒業後も相談可能な場合あり
職種・職場選びのポイント

発達障害がある方にとって、長く働き続けるためには仕事内容だけでなく職場環境との相性が重要です。
自分の特性を理解したうえで、向いている職種や働きやすい条件を見極めましょう。
特性を活かせる職種の探し方
ASD(自閉スペクトラム症)
集中力や正確さを活かせる仕事が向いています。
例:データ入力、プログラミング、品質管理、研究補助など。
手順やルールが明確な作業だと力を発揮しやすい傾向があります。
ADHD(注意欠如・多動症)
動きや変化のある業務が向いています。
例:営業、イベント運営、接客、配送業務など。
短時間集中を活かし、興味のある分野でモチベーションを維持できる仕事が合いやすいです。
LD(学習障害)
読み書きや計算に負担がある場合は、そこを補えるツールや分業体制が整っている職場が理想です。
例:製造補助、クリエイティブ作業、手作業系の仕事など。
職場環境の確認
応募前や面接時に、働く場所の雰囲気や設備をチェックしておくと安心です。
- 騒音や照明が強すぎないか(感覚過敏への配慮)
- 休憩スペースが確保されているか
- 業務マニュアルや作業手順書があるか
- 周囲との距離感やコミュニケーションの取り方が自分に合っているか
可能であれば、職場見学や短期実習を通して事前に体験することをおすすめします。
雇用形態と働き方の選択肢
- 正社員:安定して働けるが責任や業務範囲が広い場合が多い
- 契約社員・パート:業務が限定されやすく、段階的に働き方を広げやすい
- テレワーク:移動や環境変化の負担を減らせるが、自宅での自己管理が必要
まずは短時間勤務や試用期間を経て、徐々に勤務時間や業務量を増やす働き方も選択肢に入れると安心です。
一般就労以外の選択肢

発達障害があるからといって、働く場が「一般就労」だけとは限りません。
特性や体調、ライフスタイルに合わせた選択肢を知っておくことで、より安心してキャリアを築くことができます。
福祉的就労(就労継続支援A型・B型)
- A型事業所
-
雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる形態。
週20時間程度の勤務から始められることが多く、福祉的サポートを受けながら就労スキルを磨けます。 - B型事業所
-
雇用契約は結ばず、作業に応じた工賃が支払われます。
体調や特性に合わせて柔軟に働け、就労経験が少ない方や体力に不安がある方に向いています。
進学・就職準備型煌光学園豊田キャンパスでは、施設内にグループ法人が運営している就労継続支援A型・B型キラキラがあります。
キラキラで働く人々を見たり、職場体験に訪れたりすることで、自分の適正や将来で働くビジョンを持ちやすいです。
在宅ワーク
通勤の負担や職場の刺激(騒音や照明)を避けられる働き方です。
例:ライティング、デザイン、プログラミング、データ入力など。
ただし、自宅での自己管理や納期管理が求められるため、スケジュール管理が苦手な場合は支援者のフォローやツールの活用が必要です。
職業訓練校や専門学校でのスキルアップ
すぐに就職せず、学び直しや資格取得を経てから働く選択も有効です。
- 公共職業訓練(ハローワーク経由で申し込み可能)
- 民間の資格スクールやオンライン講座
特性に合った分野で技能を磨くことで、将来の就職先の幅が広がります。
周囲の大人ができるサポート

発達障害のある人の就職活動は、本人だけで進めるのではなく、保護者・教員・支援員がチームとなって支えることで成功率が高まります。
サポートは就職前だけでなく、就職後の職場定着にもつながります。
情報収集と選択肢を提示する
本人が必要な情報をすべて自分で集めるのは負担が大きいため、周囲が求人情報や制度の内容を調べて整理してあげるとスムーズです。
- 一般求人と障害者雇用枠の違いを比較
- 支援制度(就労移行支援、職業センター、ハローワーク専門窓口など)の説明
- 職場見学や職業体験の機会を探す
日常生活スキルの定着支援をする
働くうえで必要な生活習慣や対人スキルも、就職活動と同時に整えておくことが重要です。
- 生活リズムの安定(規則正しい起床・就寝)
- 身だしなみや言葉遣いの練習
- 時間管理や予定の確認方法(スマホのアラーム、手帳などの活用)
就職後の定着支援とフォロー
採用後も、環境に慣れるまでのサポートが欠かせません。
- 定期的に本人の状況をヒアリング
- 困りごとがあれば早めに企業や支援機関に相談
- 必要に応じて就労定着支援(福祉サービス)を利用
特に入社後3〜6か月は職場環境や業務内容に慣れる過程でストレスが高まりやすく、離職率も上がる時期です。早期のフォローで離職防止につながります。
まとめ|特性理解と支援活用で広がる就職の可能性
発達障害があるからといって、就職の選択肢が限られるわけではありません。
大切なのは、自分の特性を理解し、それを活かせる職場や働き方を見つけることです。
就職活動の流れを押さえ、支援制度や専門機関を活用することで、職場選びから応募、面接、そして就職後の定着まで、一貫したサポートを受けられます。
保護者や教員、支援員がチームとして関われば、本人の負担が軽減され、安心してキャリアをスタートできます。
進路や働き方に迷ったときは、一般就労だけでなく、福祉的就労や在宅ワーク、スキルアップ期間など、幅広い選択肢を検討してみましょう。
特性を理解してくれる環境と適切なサポートがあれば、誰もが自分らしく働く未来を築けます。
煌光学園では、発達特性を抱える中高生に向けて、進学・就職に特化した支援を行っております。
進学のための学習支援、就職のためのソーシャル・スキル・トレーニングのほか、社会生活で必要なスキルを培い、進路選択をサポートしています。
また、eスポーツを取り入れ、グループワークやコミュニケーションを取りながらお子様が楽しく通所できるような放課後等デイサービスです。
お子様の特性一人ひとりに合わせて作成したオーダーメイドの個別支援計画に基づき、将来のために必要なスキルを身につけるサポートをします。
お子様のやる気を引き出すeスポーツ設備も完備!無料体験・見学受付中です!
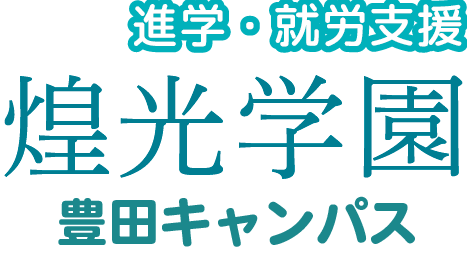

バナー-2.jpg)